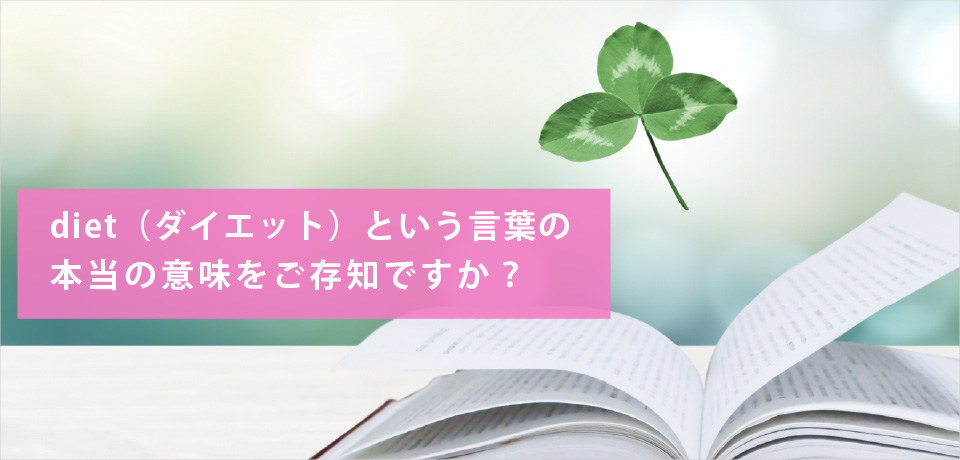
初めてコラムを書かせていただきます。これから『ダイエット』に関連する内容を連載させていただく予定ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
まずは、『ダイエット』という言葉の意味を整理しておきましょう。皆さんは『ダイエット』という言葉を聞くとどのようなことを連想されますか?恐らく多くの方は「減量すること」あるいは「減量のために食事制限すること」という風に捉えておられるのではないでしょうか?
わが家にある古い(私が受験勉強に使っていた)英語の辞書(研究社 新英和辞典)で『diet』という単語を引いてみると、
- 日常の(飲)食物:a meat diet 肉食、a vegetable diet 菜食
- (治療・体重調節のための)規定食、特別食、食餌(しょくじ)療法、食養生:on a diet 規定食をとって、食餌療法をして/go on a diet 食餌療法を始める
と書いてあります。(他にthe Dietと書いて国会、議会という意味もあります。)
ちょっと漢字や表現が古いですね。
それはさておき、『diet』という単語には、確かに「食事療法」という意味はあるのですが、必ずしも減量のためだけではありません。そして何より真っ先に出てくる意味は「日常の(飲)食物」なのです。
例えば、「沖縄はかつて平均寿命全国1位の長寿県だったが、2015年には男性36位となってしまった。これにはアメリカンダイエットが大きく影響している。」という表現があるのですが、ここでいう『アメリカンダイエット』はアメリカ式の(減量のための)食事療法ではなく、アメリカ人が普段から口にしている日常の飲食物、つまりハンバーガーに代表されるファーストフードや砂糖がたくさん入った炭酸飲料などを指しています。
こちらのコラムでは、減量に関する話題だけではなく、普段の食事内容に関する話題も取り上げて参ります。
とは言え、まず1回目は、多くの方が関心を寄せておられるであろう「減量方法」に関する内容を書かせていただきますね。

私はある時、こうおっしゃる方に出会いました。「私の趣味はダイエットで、特技はリバウンドです。」と。これを初めて聞いた時、「言い得て妙!」と思いました。ダイエット(減量のための方策)とリバウンドを繰り返しておられる方がたくさんいらっしゃるのは事実です。
世の中には数々の『ダイエット』法がありますね。過去に流行したものも振り返ってみますと、『りんごダイエット』、『ゆでたまごダイエット』、『耳つぼダイエット』、『ビリーズブートキャンプ』、『低糖質ダイエット』、最近では『酵素ダイエット』や『間欠的ファスティング(プチ断食)』などなど。
なぜこのように次々と流行の『ダイエット』法が生まれるのでしょうか。また、実際にこれらの『ダイエット』法は効果があるのでしょうか?結論から申し上げると、短期間であれば、恐らくどの方法でも効果はあります。しかし、問題はなかなか長続きしない事です。あるいは中には長く続けること自体が、実際には健康を害することにつながるため、もともと短期間しか行うべきではないものも含まれています。
以前、みのもんたさんの『午後は○○おもいッきりテレビ』という番組がありましたが、その番組の特集で「健康に良い○○。」と取り上げられた食材は、その日のうちにスーパーで完売するという現象が起きていました。いつの時代も人々は、「これさえやっていれば、これさえ食べておけば・・・」という食材や方法を求めているのでしょうね。

ところで私はかつて健診センターで仕事をしていたことがあります。健診では最後に医師から説明を受けますよね。その説明をするお仕事です。一通りの結果説明をした後、「それではこれから栄養指導がありますからね。」と伝えると、「いやあ、栄養指導は去年も聞きました。どうせ言われることはわかっています。朝ごはんを食べなさいとか夜中のラーメンはいけませんよとか。ええ、ええ、もうわかっています。どうせ怒られるようなことしかやってないんで。今日はもうお腹が空いて死にそうなので、早くお昼ご飯を食べて帰りたいです。栄養指導はキャンセルしてください。」とおっしゃる方が結構いらっしゃいました。
張り切って予め栄養指導せん(医師から管理栄養士さんに宛てて、どのような内容の食事指導をして欲しいか依頼するための書類)を書いたことを後悔しながら、毎回破棄する羽目に・・・。そのうち私も少々賢くなって、栄養指導せんを書く前に、その方に「今日は栄養指導を受けて帰られますか?」と尋ねるようになりました。興味深いことに、体重過多や血液データの良くない方(つまりは是非とも栄養指導を受けていただきたい方)に限って、栄養指導をキャンセルして、ランチを食べるために早々に去って行かれる傾向がみられました。
どうしてそうなるのだろうかと、私なりに考えてみたのですが、結局、1回限りの短い時間での栄養指導では、誰もが知っているような教科書通りの内容しか伝えられないからではないのかなと推測しました。
当時、健診結果を説明する時に、当日の検査結果だけでなく、その1年前、2年前の結果もパソコン上で見る事ができました。それら3年間分のデータ(例えば血圧の値や血液検査結果など)を比較してみると、以前に比べて著しく悪化している、または逆に改善している、あるいは悪い意味でV字回復している場合などがありました。
そういう時に、私はその方々に、この1~2年間で何か生活に変化が起きたかを尋ねるようにしていました。すると、「今年から単身赴任になりました。」「去年結婚したんです。」「仕事が変わって週ごとに夜勤と日勤を繰り返すようになって・・・。」などと、家族構成や生活リズムが変化していることがわかりました。本来であれば、それらをじっくり聴取した上で、その方に合った栄養指導をするべきですが、限られた時間内では難しいことを痛感しました。
『ダイエット』を試みる方の大半が失敗するのもこれと同じ理由だと思います。人によってライフスタイルや好みが異なるのに、皆が同じ方法で、しかもこの方法さえやっていれば成功すると信じているからうまくいかないのです。まずは自分のライフスタイルや好みに合った方法を見つけましょう。自分一人では難しいという人は、手伝ってくれる人や場所を探しましょう。中にはストイックに自分を律することができる方もいらっしゃいますが、私も含め多くの方は自分一人では挫折しやすく、誰かに適度に管理され、励まされる方がモチベーションが続くことでしょう。

これまでの生活が今の自分を作っているのですから、同じ生活を続けるのであれば変化は期待できません。確かに人間はそんなに簡単には変われません。しかし、決意して意識が変われば行動が変わる場合もあります。初めから壮大な計画を立てず、少しだけ頑張ればできそうなことから、取りかかってみましょう。
ちなみに、私自身は「がまんは2週間が限界。」と思っています。例えば食べたい物を完全に禁止したり、逆に健康や減量に良いからといって、自分では美味しいとは思えない物を食べ続けたりするような「がまん」は長続きしません。初めからできない約束はしない方が良いですね。できなかった時に落ち込んで、かえってリバウンドを促進してしまいますから。美味しく楽しく自分らしく減量し、かつ適正体重を維持できた時に初めて、「ダイエット(ここでは減量のための方策を指す)を成功させることができた!」と言えるでしょう。
次回は「栄養8割 運動2割」というテーマでお話しする予定です。
コラムニスト|ライフサポートクリニック広島 院長:新宅 恵子
所在地・アクセス
〒732-0055 広島市東区東蟹屋町7‐34 重見ビル3F Tel:082-259-3345- 広島駅新幹線口よりあけぼの通りの方向へ徒歩5分
- 広島駅新幹線口より県道84号線経由で約3分

院長 新宅 恵子
開業のきっかけは,私と同じように悩んでおられる方々のお役に立ちたいという思いからでした。何に悩んでいたかと申しますと,「子育て」と「産後の肥満」です。自分とは似ても似つかぬ個性のわが子と向き合うのは大変でした。子どもを治して欲しいと思ったことがありますが,学んでいくと,結局直さなくてはいけないのは自分たち,親の方でした。
子育てに欠かせない3要素は「愛情と栄養とトレーニング」というコンセプトに基づき,児童・思春期精神科を開業しようと決意した際,自身の肥満是正の経験と,かつて健診センターで仕事をしていた時のジレンマを思い出し,大人にも子どもにも重要である身体への栄養を重視したダイエット外来(栄養外来)も併設することを思いつきました。
開業以来,児童・思春期精神科外来には相談にみえる方が年々増加し,医師一人体制では限界が参りました。徐々にお一人にかける時間を減らさざるを得なくなり,当初目標としていた「栄養」に関してはほとんど触れる暇が無い状態でした。
児童・思春期精神科の初診受付待ちが4ヶ月となった2020年12月から一時受付を休止し,改めて通院中の子どもさんやご家族の基本的生活習慣(栄養,睡眠,運動など)の見直しに取りかかりました。
2021年2月からはダイエット外来(栄養外来)を保険外診療としました。10回程度の教室に通っていただくようなスタイルで栄養について楽しく学んでいただきながら,ご自身の健康管理にお役立ていただくようサポートしています。
(児童・思春期精神科外来は2021年11月現在,初診受付を休止しております。)
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2022/02/02
2022/02/02今年もよろしくお願い申し上げます。第3回コラムは実は『正月太り』の方が良かったかなとも思いつつ、前回予告してしまいましたので、『産後太り』についてお話しいたしますね。
そもそも『産後太り』って何でしょう?妊娠中に体重が増えるのは当たり前ですよね。その増えた体重や変化した体型が、出産後に一定期間経った後も元の(妊娠前の)体重や体...続きを読む
-
 2021/12/20
2021/12/20今回で2回目のコラムとなります。最初に前回のおさらいをしておきましょう。
前回、『ダイエット』というテーマでコラムの連載を開始するにあたり、最初に『ダイエット(diet)』という言葉の意味を整理しておきました。英単語の『diet』には...続きを読む
-
 2022/02/28
2022/02/28前回は「産後太り」Part1~その前に~と題して『妊娠中』と『妊娠前』の女性の体重についてお話しさせていただきました。今回はその続きです。
前回コラム:「産後太り」Part1 妊婦の体重増加(母体側の要素)は赤ちゃんの発育のために必要不可欠なものなのですが、実際には必要以上に太ってしま...続きを読む
-
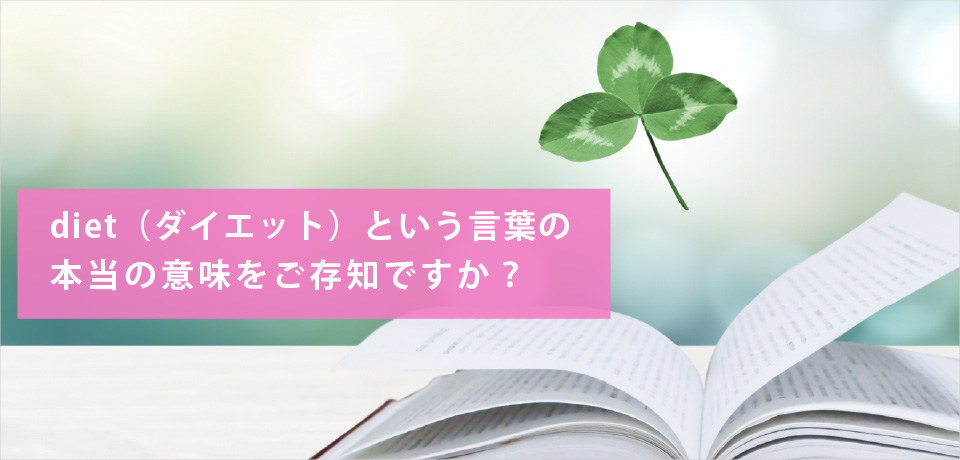 2021/11/26
2021/11/26初めてコラムを書かせていただきます。これから『ダイエット』に関連する内容を連載させていただく予定ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
まずは、『ダイエット』という言葉の意味を整理しておきましょう。皆さんは『ダイエット』という言葉を聞くとどのようなことを連想されますか?恐らく多くの方は「減量する...続きを読む





