
子どもとの良い関係を育てていくためには、なんでも叱って言うとおりにさせるのではなく、年齢に合わせて子ども自身が納得できるように言い聞かせるのが大切…とはいえ、子育ての現場では叱らざるを得ない場面は多々ありますよね。
ただ、同じ「叱る」といっても、子どもの発達段階によっては全く伝わらず、マイナス効果を与えてしまうことも。
そこで今回は「叱り方に迷う」という声が多い、赤ちゃん・2歳~3歳・小学生について、年齢に応じた叱り方のポイントや避けた方がいい叱り方の例を場面ごとにお伝えします。
赤ちゃんの叱り方

0歳から1歳前半頃の赤ちゃんには、そもそも「叱る」はほとんど必要なく、その場で危険を伝えるだけで十分といえます。
たとえば熱いものに触ろうとした時や、他の赤ちゃんの髪の毛を引っ張った時、道路に出てしまいそうになった時などは、真剣な声で「危ないよ!」「ダメ」と短く言って、手をとってやめさせます。
この時期の赤ちゃんに「なぜ危ないのか」を言葉で説明してもまだほとんど理解できませんが、ママやパパがいつもと違って笑っていない、低いトーンでなにか言われた…などで良し悪しを感じとることはできます。
逆にやってはいけないのは、赤ちゃんが泣くほど怒りの感情を出して大声で叱ること。
目を離している間に食べ物をぐちゃぐちゃにしてしまったなど「困るけど危険ではない行動」を見つけた時は思わずカッとしてしまいますよね。
しかし、0~1歳代で手近なものを触りまくるのは成長のための本能である上、「これは触ってもいい」「これはダメ」を大人と同じように判断するのは困難と考えられています。
厳しく叱られても、赤ちゃんの中では「理由もなく怖い目に遭わされた」と受け止めてしまうため、度重なると大人への不信感や恐怖感が残ってしまいます。
「それはママ困る、やめようね」と真面目に伝えたら、赤ちゃんを安全な場所に離してさっさと片付けるだけでOKです。
2歳~3歳児の叱り方

2~3歳になると「なぜダメなのか」という理由を説明すれば、少しずつ理解できるようになってきます。その一方で感情のコントロールはまだ未熟なため、色々な場面で叱られるような行動をとります。
たとえば他の子のおもちゃをむりやり奪い取ってしまったような時は、あくまでも端的に「取らないよ!つぎ貸してって言おうね」などと説明し、おもちゃを返して落ち着くまでその場を離れます。
イヤイヤ期とも重なるこの時期は、言い聞かせてもなかなかすぐには気持ちを切り替えられないため、ママやパパも根気よく付き合うのが大変ですよね。
しかし、この時期やってはいけない叱り方は、堪忍袋の緒が切れて「そんな悪い子はうちの子じゃない!」「もうママ、〇〇ちゃんなんて大嫌い」と人格否定すること。
幼児期にこのように言われた記憶がある人に「親からそう言われた理由はなんでしたか?」と聞いたアンケートでは、8割の人が「わからない/覚えていない」と答えていますが、それでも深く傷つき悲しかった記憶だけは残っているそうです。
あくまでも「それは〇〇だからやめようね」と、行動について伝えるようにしたいですね。
小学生の叱り方

小学生になると、宿題や習い事など「やらなくてはいけないこと」が増え、交友関係も広がります。
約束の時間までに遊びから帰ってこない、宿題が終わってからゲームをすると言ったのに宿題ができていないなど、ルールを守らなかった時は、まずは「どういう約束だった?」「その約束はなんでそう決めたんだっけ?」と本人に思い出させると良いですね。
そのためには、最初にルールを決めるときから、一緒に相談したり理由を伝えたりして、子ども本人が納得したりしていることも大事です。
また小学生になると、担任の先生などから連絡があって初めてトラブルを知るというケースも増えてきます。クラスの子とケンカして手を出してしまった…などと聞いて対処に悩むママ・パパもいるかもしれません。
このとき、特に避けたい叱り方は、子ども本人の話を聞かずに一方的に叱ることです。
まずは落ち着いて、なぜそうなってしまったのかを聞くと良いですね。
たとえば「遊びの中で相手の子がズルをして、注意してもやめないから、頭にきて悪口を言った。向こうが怒って押してきたから押し返したら、力が入りすぎて転ばせてしまった」というのが事実であれば、悪口を言ったことや強く押し返したことは良くないですが、子どもにも言い分があることが分かります。
ここで頭ごなしに「何やってるの!」「全部お前が悪い」と叱ると、子どもは話を聞いてもらえないと感じて、次から何かあっても隠そうとするかもしれません。
小学生になると過去や未来という概念も備わってくるため、あくまでも「今後同じようなことが起きたらどうすればいいのか」という視点で一緒に考えるつもりで話を聞き、よくない点だけを叱るようにするのがおすすめです。
おわりに
今回は、子どもへの「やってはいけない叱り方」を解説しました。
でも、考えてみると「あくまでも行動について伝え、人格を否定しない」「今度からどうすればいいか一緒に考える」などは、職場で部下や後輩に対する叱り方とほとんど変わらない…と感じた方も多いのではないでしょうか?
子どもも大人と同じ1人の人格を持った人間なのですが、赤ちゃん時代から育てていると、ついそのことを忘れて、頭ごなしに叱ってしまうのかもしれません。
これからもずっと良い親子関係でいられるよう、なにかあった時は一歩立ち止まって、年齢に応じた適切な叱り方をしていきたいですね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2023/07/07
2023/07/077月に入ればもうすぐ夏休み。小学生のお子さんには夏休みの宿題が出されますが「うちの子、ちゃんと計画的に宿題をやれる…?」と心配なママ・パパもいるのではないでしょうか。
今回は、夏休みの宿題の計画表の作り方やお子さんへの声かけ、それでも夏休みの最後にまだ終わらない場合、親が手助けしても良いのかどうか……といった疑問にお答えします...続きを読む
-
 2022/03/09
2022/03/09「春財布は縁起がいい」「春に財布を買うとお金持ちになれる」などと聞いたことのある人は多いと思います。
でも、「春」とは具体的にいつからいつまでのことをいうのでしょうか? 今回は、春財布の買い方や年間通してお財布を購入するのにおすすめの日を紹介します。 ...続きを読む
-
 2022/07/25
2022/07/25いつの時代の親も、わが子にはしっかり勉強をがんばって、やりたい仕事に就いて活躍してほしいと願うものですよね。
しかし、それにはもちろん勉強も大切ですが、テストの点数と同じくらい、またはもっと大切な、ある「力」が必要だと近頃では言われています。 その力のことを「非認...続きを読む
-
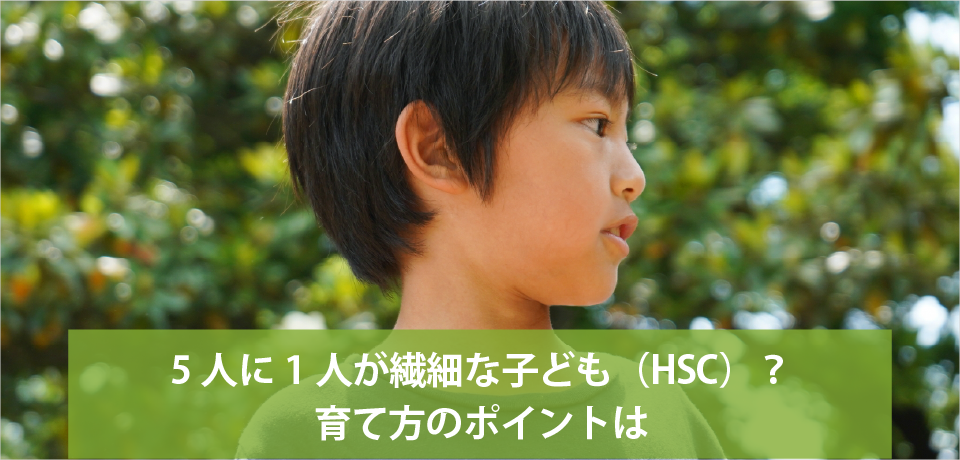 2023/12/07
2023/12/07もしかして、お子さんは、人口5人に1人の割合といわれる「HSC(Highly Sensitive Child)」かもしれません。 今回は、HSCの特徴や、...続きを読む




