
子どもの成長過程で、今まで素直に聞いていたことを聞かなくなったり口答えが増えたりする、いわゆる「反抗期」。
反抗期には、2~3歳頃の「第一反抗期」と思春期の「第二次抗期」だけではなく、実はそのあいだに「中間反抗期」もあるのをご存知でしょうか。
今回は、意外と知られていない「中間反抗期」について、時期はいつからいつまで続くのか、子どもはどんな態度をとるのか、保護者はどのように対応するといいのかなどを紹介します。
反抗期はなぜ起きる?

そもそも「反抗期」とはなぜ起きるのでしょうか?
赤ちゃんには自分と他者の区別がありませんが、どの子も少しずつ「親と自分、友達と自分は別の人格である」ということを理解し、自分なりの価値観やアイデンティティを確立させて大人に近付いていきます。
その段階で現れるのが反抗期で、親にとっては「手を焼く」「困る」と思ってしまいがちですが、子どもの心が成長するためには欠かせないステップだといわれています。
2~3歳ではまず「イヤイヤ期」ともいわれる第一反抗期が訪れます。「自分でやりたい・決めたい」という意欲が芽生えてくるため、今までのように「着替えようね」「おもちゃを片付けるよ」と指示されても「イヤ!」と拒否。内容そのものよりも、なにかを人に指示されること自体を拒否する時期です。
小学校高学年頃から中学生にかけて起きるのが第二反抗期です。この時期は思春期にもあたり、身体の変化だけでなく、ホルモンの影響で精神的にも不安定になるなど、大きく変化する時期。自分の内面にも関心が向き、自分なりの行動指針や判断基準を持つようになっていきます。そのため、今までなら素直に聞いていた指示や意見を聞かなくなったり、親の干渉を嫌って自分のことを話さなくなったりします。
中間反抗期の時期は5~10歳のうち約2年、ただし個人差あり
従来、反抗期は第一・第二のみとされていましたが、最近ではその間に「中間反抗期」があるという説があり、5歳頃から10歳頃にかけて、1~2年程度続くと考えられています。
この時期の子どもたちは通称「ギャングエイジ」とも言われ、だんだんと親や先生より友だちや仲間とのルールを優先し始めます。ただ、親から自立しようとする一方で、まだ甘えたい・頼りたい気持ちも残っていて、その葛藤が反抗的な態度として出てくると考えられています。
一般的な中間反抗期の特徴には以下のようなものがあります。
- すぐに口答えする
- 親の指示よりも友達との約束や会話を重視する
- 外ではいい子なのに家では態度が悪い
小さい頃は家族や少数の友だちとの世界だった子どもたちは、この時期だんだんと5~6人程度の固定グループで行動するようになり、社会性が大きく発達します。
外ではその仲間関係を維持するために努力する一方、まだまだ幼さも残っているため、家では外で抑制していた反動で荒れる子も。
また論理的思考能力も発達し始める時期でもあり、未熟ながらも自分なりに考えた意見を伝えようとしてきます。
ただし、中間反抗期をはじめ、反抗期の時期や度合いには個人差があり、その子の気質やたまたま親子の価値観が似ていたりすると、さほど激しい表れ方をしないこともあります。
叱る・言い聞かせる・ほっとく…親の対応は何が正解?

中間反抗期の子どもは、なにかと「違う」「うるさい」と口にしたり、不機嫌で乱暴な態度を取ることも多く、厳しく叱るのがいいのか、そういう態度は良くないと向き合って言い聞かせるのがいいのか、言い争いになるくらいならある程度放っておくのがいいのか…迷いますよね。
中間反抗期の小学校低学年・中学年は、まだ厳しく叱れば泣いてしまう子もいて、親の力で言うことを聞かせられるかもしれません。
しかしこの時期、子どもは今まで唯一正しいと信じていた親の価値観以外に、友達や仲間を通じて新しい価値観を取り入れようと模索しています。
それが犯罪や人権侵害などにつながるものでない限り、押さえつけずに、なぜそう思うのかを聞き、受け入れていく必要があります。そうでないと今後意見の違いが出てきたときも親子で話し合う習慣が身に付かないからです。
頭ごなしに親の言うとおりにさせ続けていると、第二反抗期を迎えたとき、肉体的に成長した子どもは暴力で自分の主張を通したり、不満を噴出させたりするようになっていくおそれもあります。
弱い者いじめや差別的な発言などはもちろんこれまで通り叱るべきですが、ちょっと言葉づかいが乱暴とか、注意したときに「ママだって〇〇してるじゃん!」と言い返すなどは、ある程度目をつぶっておきたいですね。
ただし、最近急に何も話してくれなくなった、行動や言葉がひどく荒れている……という場合、単なる中間反抗期ではなく、学校や学童保育・スポーツ・習い事などの集団生活の中でトラブルを抱えている可能性もあります。
念のため、信頼できる人に頼んで様子を見てもらうなど、子どもの周りで問題が起きていないかも確認しておきましょう。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
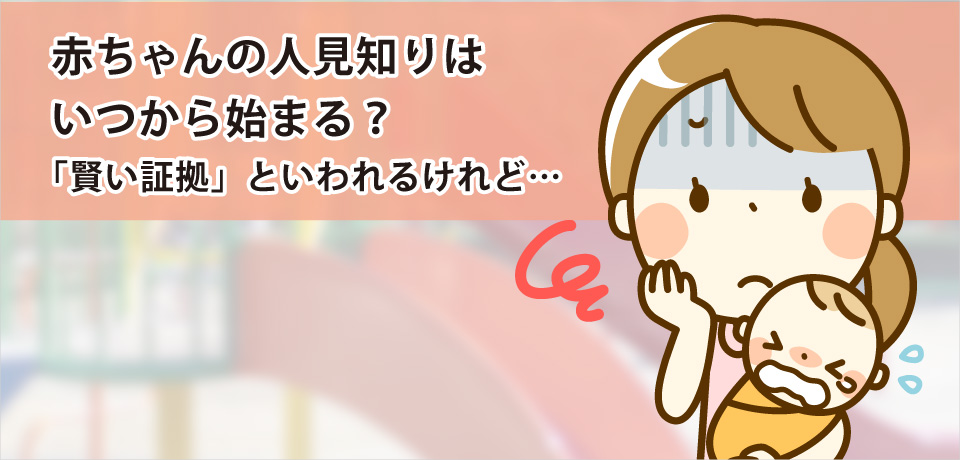 2021/04/19
2021/04/19赤ちゃんが、家族以外の人に話しかけられるとママにしがみついて顔を隠してしまったり、だっこしようとすると泣いて嫌がったりする「人見知り」。
ママからすると、あまり赤ちゃんの人見知りが強いと、相手に対して気まずい思いもするし、人に預けにくくて困ってしまいますよね。 その一方で、あまり人見知りをし...続きを読む
-
 2024/06/04
2024/06/04成長にともない「そろそろ小児科じゃなく、内科に行くべき?」と考える人も多いと思います。 しかし具体的に何歳になったら小児科を卒業するべきなのか、はっきりし...続きを読む
-
 2022/07/25
2022/07/25いつの時代の親も、わが子にはしっかり勉強をがんばって、やりたい仕事に就いて活躍してほしいと願うものですよね。
しかし、それにはもちろん勉強も大切ですが、テストの点数と同じくらい、またはもっと大切な、ある「力」が必要だと近頃では言われています。 その力のことを「非認...続きを読む
-
 2025/05/09
2025/05/09育児相談などでよく言われる「ママは困ったらどんどん周囲の人を頼りましょう」というアドバイス。
たしかにその通りではあるのですが、いざ困った場面になると「こんなこと頼んだら迷惑じゃ…」「頼んで嫌な顔をされるくらいならガマンしよう…」など、誰にも頼れないと感...続きを読む




