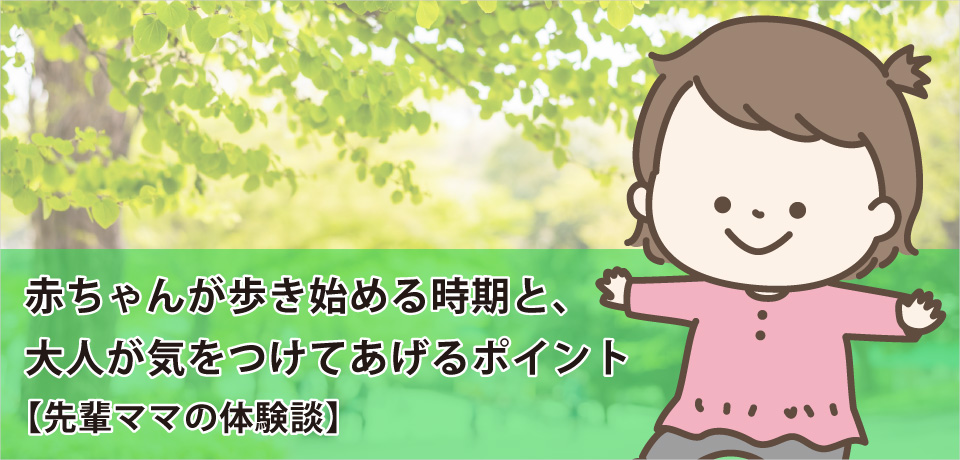
赤ちゃんがハイハイからつかまり立ち、伝い歩きなどを始めたら、ママやパパは「もうすぐ歩くのかな!?」とドキドキワクワクしますね。
また「まわりの同い年の子は歩き始めているのに、うちの子はまだ…」と心配になっている人もいるかもしれません。
今回は、赤ちゃんが一般的に歩き始める時期と身体の発達について、また歩き始めの赤ちゃんのために気をつけてあげたいポイントなどを解説します。
また「うちの子は歩き始めるのが早かった」「ゆっくりだった」というママの体験談から、成長後のようすも紹介します。
赤ちゃんはいつから歩く?
赤ちゃんは一般的にはいつごろから歩くのでしょうか。
全国のママに配布される母子手帳でみると、それぞれ以下のページに「できるようになった時期」を記入する欄があります。
● 伝い歩き…1歳
● ひとりで上手に歩く…1歳6か月
上記はあくまでも目安で、実際は個人差がとても大きいのですが、おおよそ生後1歳~1歳半頃に歩き始める子が多いといえます。
赤ちゃんの手をとって歩く真似をさせると今にも歩けそうに見えますが、実際には次のようなさまざまな身体的発達が揃ってはじめて1人で歩くことができます。
- 足だけでなく背筋や腹筋、腕などの筋肉がしっかり発達している
- 股関節や膝、足首の関節がしっかりしている
- 転びそうになったときに手で支えて頭や顔を守る「パラシュート反応」、身体が倒れそうになると足を出して支える「ステッピング反応」などの姿勢反射があらわれる
筋肉や関節はしっかりハイハイしている時期に発達します。また上記の姿勢反射は自然に時期が来ればあらわれ、訓練で早めることはできません。
参考
先輩ママの体験談で知る「早い子」「ゆっくりな子」の成長後は?
今回は、2人のママに、お子さんが歩き始めた時期と、成長したときの様子を教えてもらいました。
Uさん(歩き始めは生後10か月、現在小学校2年生のママ)は、
と話します。
と、歩く準備として必要なハイハイがしっかりできる環境を整えたそうです。
いっぽう、
というKさん(歩き始めは1歳5か月、現在5歳)は、公園などで会う同い年の赤ちゃんがどんどん歩けるようになるので内心焦ったそうです。
現在は幼稚園の年長さんになったお子さんのようすは、
だということです。
歩き始めの赤ちゃんに気をつけてあげること
赤ちゃんが歩き始めたばかりの時期は、
- 転んだ時にぶつかりそうな家具の角にはコーナーガードやクッションをつける
- 階段の上下や玄関に降りる段差などにはベビーゲートをつける
- つかまったときに倒れてきそうな不安定な家具やコードは固定する
など、家の中の安全対策を。
外で歩くための靴も準備が必要ですが、あまり早くから購入すると実際に歩きはじめたときの足のサイズと合わないことがあるため、様子を見て、足にフィットするサイズを選びましょう。
サンダルタイプやデザイン重視の靴はかわいらしいですが、ケガや歩きにくさにつながるため、つまさきが広めのもの、かかとがしっかりしたもの、靴底が指の付け根あたりで自然に曲がるやわらかさのものを選びましょう。
参考
おわりに

「這(は)えば立て、立てば歩めの親心」という昔の言葉があります。
わが子の成長は楽しみですし、まわりの赤ちゃんが歩き始めるとつい、「早く歩かないかな」と焦ったり不安になったりするかもしれません。
しかし、食べることや歩くことはほんとうに個人差が大きいもの。
今回体験談をお聞きしたママ以外でも「歩き始めは早かった(または遅かった)けど、成長したらなにも影響がなかった」と話す人はたくさんいます。
赤ちゃんが順調に成長しているのであれば、ぜひその子のペースを大切に見守ってあげて下さいね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2023/01/27
2023/01/27保育園や幼稚園では毎年2月の節分(せつぶん)が近付くと、みんなで豆まきをしたり、手作りの鬼のお面をお子さんが持ち帰ってきたりしますよね。
でも、お子さんにとっては「なんで鬼がくるの?」「せつぶんってなに?」と不思議に思えるかもしれません。 そこで今回はママ・パパ向けに、節分の意味や豆まき・恵...続きを読む
-
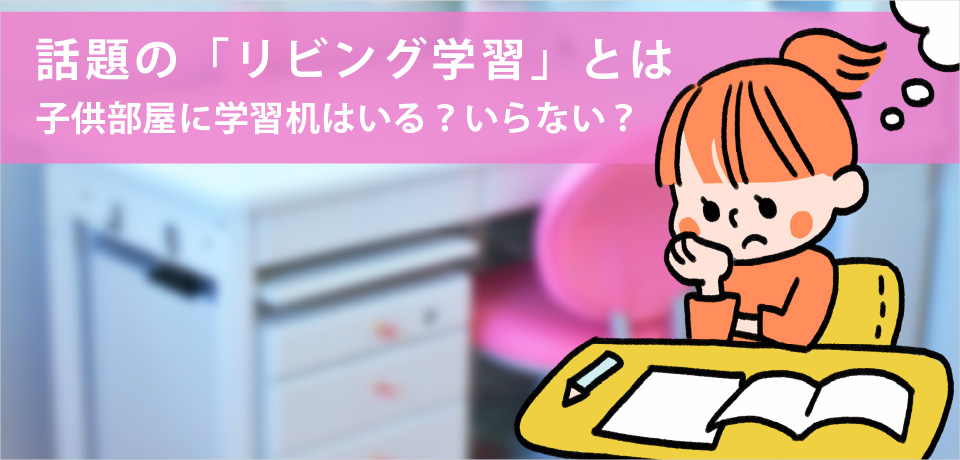 2021/11/30
2021/11/30年末も近づき、もうすぐ小学校に入学するお子さんのいるお宅では入学準備が進んでいることと思います。
学習机の購入を検討しているご家庭も多いと思いますが、ふと「小学校の宿題って、最初から自分の部屋でできるものかしら」と疑問に思うことはないでしょうか。 最近...続きを読む
-
 2023/04/24
2023/04/24この春お子さんが小学校に入学したご家庭の皆様、ご入学おめでとうございます!
小学校では初めての体験がいっぱいですが、朝、近所の子供たちが公園などに集合してみんなで学校に行く「集団登校」もそのひとつですよね。 「慣れるまでのあい...続きを読む
-
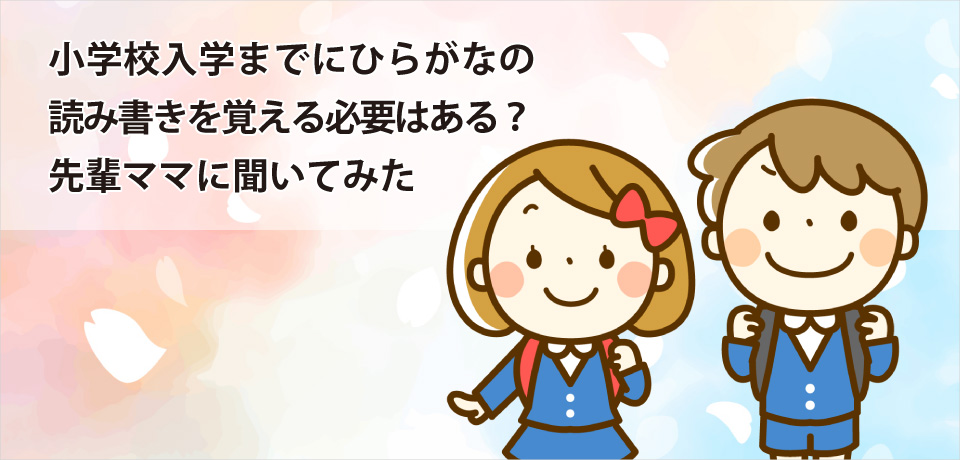 2021/03/26
2021/03/264月はピカピカの小学校一年生が入学する季節。親御さんとお子さんにとっても大きく環境が変わる時期です。
「給食ちゃんと食べられるかな」 「新しいお友だちとうまくやれるかな」 親御さんが気になることはたくさんあると思いますが、やはり学習面ではじめての授業につ...続きを読む




