
昨年の夏頃のメールです。今はコロナ禍なので家の中にいることも多くもっともっと、大変なのかもしれません。
4歳男児の母からのメール
個人を特定できないように配慮したうえで、その時の返信メールをこの場で紹介します。同じような悩みをお持ち方が多くいるのではないかと思います。
私からの返信
ご心配のことと思います。
メールなのでうまく伝えられるかどうか心配ですが、できるだけわかりやすく書きますので最後まで読んでみてください。
いろいろなものに注意を奪われて親の言葉が入らない(不注意性)、じっとしていることが苦手で常に動き回ったりおしゃべりが止まらなかったり(多動性)、自分がやりたいと思ったらその気持ちを抑えることが苦手(衝動性)。これらの特性を生まれつき持っている場合、ADHD(注意欠如・多動症)の可能性を考えてみる必要があります。
スーパーマーケットで欲しいものを買ってもらえないときに大声で泣きじゃくり、床で手足をバタバタして手が付けられなくなるようなこともしばしば。危険な状況に対してもあまり恐怖心がなく、手すりによじ登ったり、階段の高いところに平気で上がったりします。道路の左右を確認もせずに、道路に飛び出すようなこともしばしばあります。大人が注意しても、危険な行為が繰り返されます。
子どもが親の言うことを聞かないと、親のしつけが悪いと思われがちですが、そうではありません。もともとの生まれつきの特性が要因となっていると考えられます。生まれつきの脳の機能の問題として不注意性、多動性、衝動性があり、家庭生活や学校生活、職業上困難がある場合にADHDと診断されます。
この場合、重要なのは叱るときに感情的にならないこと。頭ごなしに大声でがみがみ言っても子どもを興奮させるだけです。
子どもを叱る時は、一呼吸おいて冷静に叱るようにします。低い声、子どもの顔を見て。はっきりとした口調で短くきっぱりと叱ります。言いたいことがたくさんあっても手短に伝えるようにしてください。
その際、子どもの言い分や気持ちを受け取りながら、今の行動が正しくないことを伝えます。そして、頑張り屋なところや明るいところなど「良いところ」をほめることも忘れないようにしてください。
最後に
周りの大人が発達障害に早く、気づき、適切な支援を行うことで、子どもの生きづらさはかなり改善されます。ADHDに対しては、薬物療法、環境改善、行動療法の3つのアプローチで対応すると効果があります。わかりやすく言うと行動の改善に有効な薬、集中しやすい環境づくり、ほめながら適切な行動を増やしていく対処法を取り入れることが今後の取り組みとなるでしょう。
一般的には、ADHDの心配があると思ったときには医療機関や地域の子育て支援センターなどに相談し、適切な支援へとつなげていきます。医療機関の受診などがためらわれるときには、幼稚園や保育園、学校の先生に相談することが重要となります。
コラムニスト

公認心理師・臨床心理士・特別支援教育士スーパーバイザー
竹内 吉和
私が大学を卒業してすぐに教師となって教壇に立ってから30年が過ぎ、発達障害や特別支援教育について講演をするようになって、10年以上が経ちました。特別支援教育とは、従来知的な遅れや目が不自由な子供たちなどを対象にしてきた障害児教育に加えて、「知的発達に遅れがないものの、学習や行動、社会生活面で困難を抱えている児童生徒」にもきちんと対応していこうと言う教育です。
これは、従来の障害児教育で論議されていた内容をはるかに超えて、発達障害児はもとより発達障害と診断されなくても認知機能に凹凸のある子供の教育についても対象としており、さらに子供だけでなく我々大人も含めたコミュニケーションや感情のコントロールといった、人間が社会で生きていくうえにおいてもっとも重要であり、基礎的な内容を徹底して論議しているからであるととらえています。
そのためには、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握して適切な教育的支援を行う必要があります。ここで、単に教育とせず、教育的支援としているのは、障害のある児童生徒については、教育機関が教育を行う際に、教育機関のみならず、福祉、医療、労働などのさまざまな関係機関との連携・協力が必要だからです。また、私への依頼例からもわかるように、現在、小・中学校さらに高等学校において通常の学級に在籍するLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、知的に遅れのない自閉症(高機能自閉症・アスペルガー障害)などの児童生徒に対する指導及び支援は、喫緊の課題となっており、これら児童生徒への支援の方法や指導原理や全ての幼児・児童生徒への指導は、私達大人を含めて全ての人間が学び、関わり合うための基礎といえるコミュニケーション力を考える上で必須の知識であることを色々な場で訴えています。
今までたくさんの子供たちや親、そして同僚の先生方と貴重な出会いをしてきました。また、指導主事として教育行政の立場からもたくさんの校長先生方と学校経営の話をしたり、一般市民の方からのクレームにも対応したりと、色々な視点で学校や社会を見つめてきたつもりです。ここ数年は毎年200回近くの公演を行い、発達障害や特別支援教育について沢山の方々にお話をしてきました。そして、満を持して2014年3月に広島市立特別支援学校を退任し、2014年4月に竹内発達支援コーポレーションを設立致しました。
今後は、講演、教育相談、発達障害者の就労支援、学校・施設・企業へのコンサルテーション、帰国子女支援、発達障害のセミナーなどを行っていく所存です。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
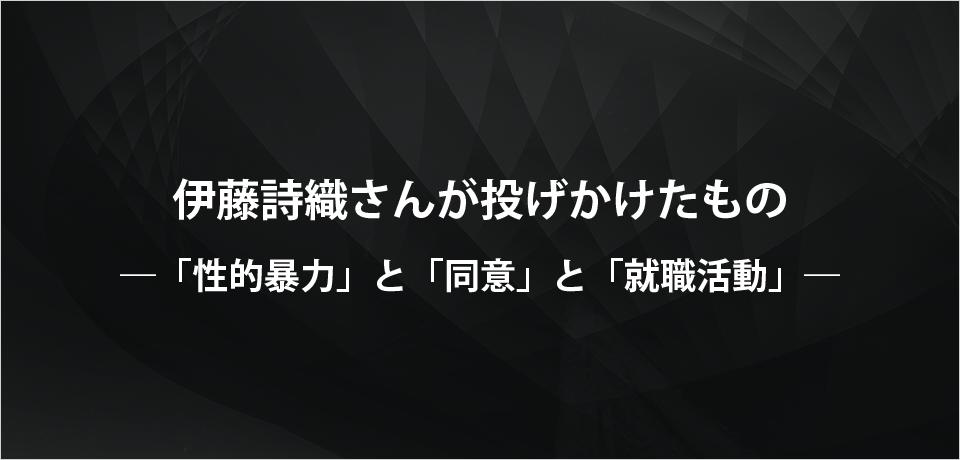 2020/01/07
2020/01/07真面目で頑張り屋の女性が自分の思うような職業に着けない。就職活動として、職を得るために、合否を握る相手に会った。
まずはじめに読者の皆さん、明けましておめでとうございます。今年もその時々で注目すべき内容や気になる事柄をわかりやすく提供していきたいと思っています。どうぞよ...続きを読む
-
 2020/09/01
2020/09/01「金曜日には好きな人とカレーを食べよう!幸せホルモンでコロナを乗り切る!!」
はじめに 「金曜日は、カレーの日」というCMがありましたね。 呉の海上自衛隊では、長期の海上勤務で「曜日感覚」が失われることを防ぐため、毎週1回カレーを部隊...続きを読む
-
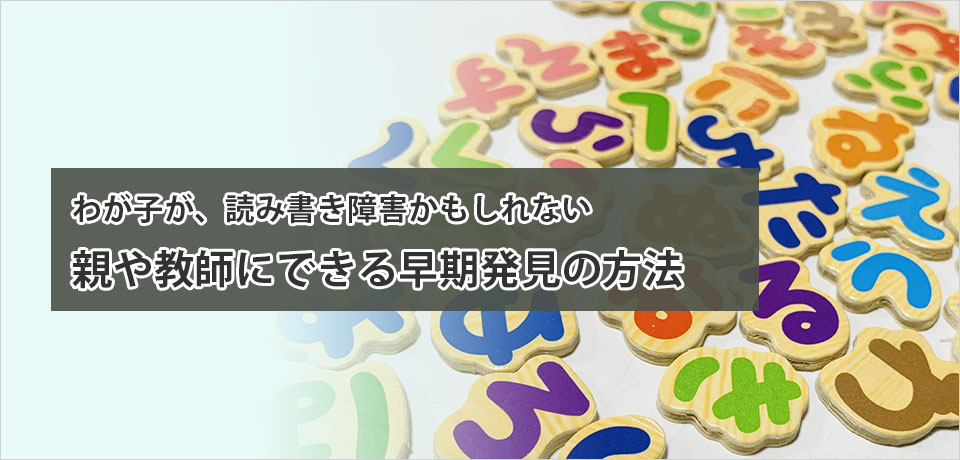 2021/03/15
2021/03/15前回、算数障害について紹介しました。多くの親御さんや学校の先生方からご意見やご相談をいただきました。今日は読み書き障害について述べたいと思います。
前回記事:わが子が「算数障害」かもしれない!その時、親は何をすればよいか!! 1.見た目にはわからない読み書き障害 読み書き障害の人の中でも、特に...続きを読む
-
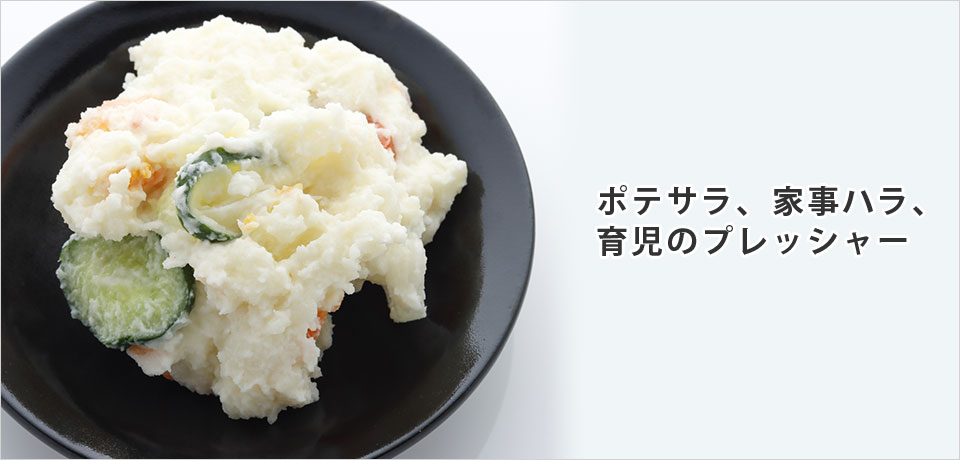 2020/07/21
2020/07/21今日のコラムは、「家事ハラ」と「性別役割分担」と「子育てプレッシャーにつぶされそうな母親の気持ち」について論じてみたいと思います。
はじめに ある日の午後、私はいつものようにぼんやりと、ネットサーフィンを楽しんでいました。 発見。「母親ならポテトサラダくらい作ったらどうだ」という記事...続きを読む




