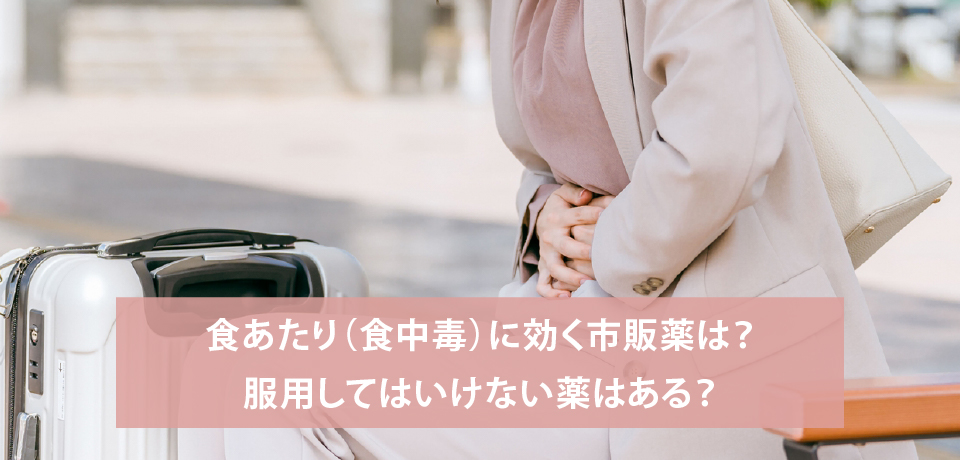
食あたりになると、腹痛や下痢などの症状があらわれます。いち早く症状を緩和したいときに便利なのが市販薬です。
しかし、市販薬の中には、食あたりのときに使うのには適していないものあるので注意しなければなりません。
今回は、食あたりに効く市販薬の選び方、食あたりに使える市販薬、セルフケアの方法などについて詳しく解説します。
食あたり(食中毒)とは
食あたりとは、食中毒の原因となる細菌やウイルスなどがついた食べ物によって起こる病気のことです。軽い下痢や吐き気で済むこともあれば、症状がひどく命に関わるようなこともあります。
細菌が原因の食あたりは6月から9月頃、ウイルスが原因の食あたりは冬に流行しやすいことが特徴です。
食あたりの原因
食あたりの原因は、細菌やウイルスです。原因となる細菌やウイルスには次のような種類があります。
| 原因となる細菌・ウイルス | 特徴 | 食あたりの原因になりやすい食べ物 |
|---|---|---|
| サルモネラ菌 | 加熱不足の卵や肉、魚などに存在します。 | 生卵、オムレツ、牛肉のたたき、レバ刺し |
| 黄色ブドウ球菌 | 人間の皮膚、鼻や口の中に存在します。 | おにぎり、弁当、巻き寿司、調理パン |
| 腸炎ビブリオ | 生の魚や貝などに存在します。 | 刺し身、寿司 |
| カンピロバクター | 加熱不足の鶏肉、飲料水、生野菜などに存在します。 | 焼き鳥、野菜、井戸水、湧き水 |
| ノロウイルス | 十分に加熱されていない牡蠣や水道水、井戸水などに存在します。 | 牡蠣、アサリ、シジミ |
| E型肝炎ウイル | 加熱不足の豚肉、内臓などに存在します。 | 豚肉、レバー |
食あたりの症状
食あたりを起こすと、以下のような症状が見られます。
- 下痢
- 腹痛
- 吐き気
- 嘔吐
- 血便
食あたり(食中毒)の症状が重くなりやすい方
次に該当する方は、食あたりの症状が重くなりやすいので注意が必要です。
- 乳児や幼児
- 高齢者
- 妊娠中の方
- 肝臓疾患やがん、糖尿病の治療を受けている方
- 鉄剤の服用が必要な貧血がある方
- 胃腸に問題がある方
- ステロイドの服用をしている方
- HIVに感染している方
- 免疫機能が低下している方
食あたり(食中毒)に効く市販薬の選び方
食あたりによって下痢や腹痛が起きた場合、市販薬に頼ろうと考える方もいるでしょう。市販にはさまざまな薬がありますが、食あたりに使えるものは限られています。
どのような薬が使えて、どのような薬が使えないのかをしっかり押さえておくことが大切です。
下痢止めや解熱鎮痛剤は使わない
食あたりの場合、腸の蠕動運動を止める働きがある下痢止めは使用できません。ロートエキス、ロペラミドなどが入ったものは避けてください。
食あたりになると下痢止めを使用したいと思うかもしれませんが、服用すると原因となる細菌やウイルスの排出が遅れて病原体が腸内に長くとどまり、症状が長引く可能性があります。
この他、解熱鎮痛剤も使用を避けましょう。解熱鎮痛剤が胃腸に負担をかけ、症状を悪化させる恐れがあるためです。
整腸剤や胃腸薬を使うのが基本
食あたりになった場合は、胃腸の動きを止めない薬を使うことが基本となります。そのため、整腸剤や胃腸薬を選ぶようにしましょう。整腸剤を服用すると、症状が早く治るとのデータもあります。
食あたり(食中毒)に効く市販薬5選
それでは、食あたりの症状に使える市販薬を5つ紹介します。
正露丸
正露丸は、腸の動きを止めずに腸内の水分バランスを整えてくれる薬です。お腹を正常な状態にし、症状を軽減します。
正露丸はさまざまなメーカーから販売されていますが、種類によっては腸の動きを止めるロートエキスが入っているものもあるため、こちらは購入を避けるようにしてください。
| 有効成分 |
●日局木クレオソート ●日局アセンヤク末 ●日局オウバク末 ●日局カンゾウ末 ●チンピ末 |
|---|---|
| 効能効果 | 軟便、下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、消化不良による下痢、むし歯痛 |
| 用法用量 |
15歳以上:1日3回、1回3粒 11歳以上15歳未満:1日3回、1回2粒 8歳以上11歳未満:1日3回、1回1.5粒 5歳以上8歳未満:1日3回、1回1粒 |
スメクタテスミン
腸内の有害物質を吸着する働きがある天然ケイ酸アルミニウムが主成分の薬です。荒れた腸の粘膜を保護する働きもあります。腸の動きを止めないため、食あたりの際にも服用が可能です。
| 有効成分 | 天然ケイ酸アルミニウム |
|---|---|
| 効能効果 | 下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便 |
| 用法用量 |
15歳以上:1回1包を1日3回まで 11歳~14歳:1回2/3包を1日3回まで |
ビオスリーH
小腸から大腸にかけて働く3つの菌が配合された整腸剤です。腸内フローラと大腸のバリア機能を改善し、軟便や腹部膨満感などの症状を緩和します。便通を整える働きもあるため、普段から服用することも可能です。
| 有効成分 |
●酪酸菌 ●ラクトミン ●糖化菌 |
|---|---|
| 効能効果 | 整腸(便通を整える)、便秘、軟便、腹部膨満感 |
| 用法用量 |
15歳以上:1日3回、1回2錠 5歳以上15歳未満:1日3回、1回1錠 |
新ビオフェルミンS錠
小腸に住み着くフェーカリス菌とアシドフィルス菌、大腸に住み着くビフィズス菌が配合された整腸剤です。小腸と大腸の両方に働きかけ、腸内環境を整えます。ヒト由来の乳酸菌を使用しているため、定着性が良いという特徴があります。
| 有効成分 |
●コンク・ビフィズス菌末 ●コンク・フェーカリス菌末 ●コンク・アシドフィルス菌末 |
|---|---|
| 効能効果 | 整腸(便通を整える)、便秘、腹部膨満感、軟便 |
| 用法用量 |
15歳以上:1日3回、1回3錠 5歳~14歳:1日3回、1回2錠 |
パンラクミン
腐敗菌などの有害細菌の増殖を抑える有胞子性乳酸菌、消化を助けるタカジアスターゼN1、有胞子乳酸菌の発育を促進するビオチンが配合された整腸剤です。消化酵素も含まれているため、食べ過ぎによる不快な症状を改善するのにも使用できます。
| 有効成分 |
●有胞子性乳酸菌 ●タカヂアスターゼN1 ●ビオチン |
|---|---|
| 効能効果 | 整腸(便通を整える)、便秘、軟便、腹部膨満感、消化不良、消化促進、もたれ、胸つかえ、食欲不振、食べ過ぎ |
| 用法用量 |
15歳以上:1日3回、1回3錠 11歳以上15歳未満:1日3回、1回2錠 5歳錠11歳未満:1日3回、1回1錠 |
食あたり(食中毒)になったときのセルフケア
食あたりになったときは、胃腸に負担をかけない生活を心がけましょう。食欲がなかったり症状が酷かったりする場合は、無理に食事を摂る必要はありません。
症状がやわらいできたら、消化の良い食事から少量ずつ始めましょう。おかゆやごはん、うどんなどがおすすめです。
また、下痢や嘔吐により脱水症状を起こしやすくなっているため、こまめに水分補給をすることも大切です。口の渇きや立ちくらみ、めまいなどの症状が出ているときは脱水を起こしている可能性があるので、経口補水液などをうまく活用しましょう。
食あたり(食中毒)になったときの注意点

食あたりになった場合は、症状を長引かせないように気をつける必要があります。具体的には、次の2つの注意点を守ることが大切です。
- 下痢や嘔吐を我慢しない/li>
- 下痢を止める薬を自己判断で服用しない
下痢や嘔吐を我慢しない
下痢や嘔吐は我慢しないでください。食あたりになると、体は有害物質を排出しようと下痢や嘔吐の症状を引き起こします。我慢すると、有害物質がかえって体内に長くとどまることになるため、症状が長引いたり悪化したりする可能性があります。
下痢を止める薬を自己判断で服用しない
下痢止めを服用すると、有害物質の排出が遅れて症状が悪化したり回復が遅れたりする可能性があります。下痢が続くからといって自己判断で下痢止めを服用するのは避けましょう。
食あたりをうつさない・うつらないためにできること
食あたりを周りにうつさない、また周りからうつらないようにするためには、以下のことを意識することが重要です。
- 食事の前、調理の前、トイレの後などは手洗いを徹底して行う/li>
- 食あたりの症状がある方は調理をしない
- 食あたりの症状がある方が使用した食器や調理器具は熱湯で消毒する
- 食あたりの症状がある方が使用した食器や調理器具は熱湯で消毒する
- 食あたりの症状がある方の衣類は別に洗う
- 食あたりの症状がある方は、最後にお風呂に入る
- 食あたりの症状がある方がいる場合は、お風呂の残り湯を洗濯に使わない
症状がつらいときは医療機関を受診しよう

食あたりの症状がひどいと、命に関わることがあります。水分摂取がまったくできない、意識がもうろうとしている、吐瀉物に血が混じっているなどの症状があるときは、できるだけ早めに医療機関を受診してください。
また、緊急性が低い場合であっても症状がつらいときは医療機関を受診して診てもらいましょう。
まとめ
食あたりは細菌やウイルスが原因で起こるものです。下痢止めを使用すると有害物質の排出が遅れて症状が悪化したり回復が遅くなったりするため、服用を避けてください。腸の動きを止めずに腸内の水分バランスを整える正露丸、整腸剤などが選択肢となります。
症状が重く出ていたり長引いていたりするときは、自己判断で市販薬を使用せず医療機関で相談しましょう。まれに重大な病気が原因で下痢の症状が出ることもあるため、気になる症状があるときは早めに相談するようにしてください。
コラムニスト

薬剤師ライター 岡本 妃香里
薬剤師としてドラッグストアで働いていくなかで「このままではいけない」と日に日に強く思うようになっていきました。なぜなら「市販薬を正しく選べている方があまりに少なすぎる」と感じたからです。
「本当はもっと適した薬があるのに…」
「合う薬を選べれば、症状はきっと楽になるはずなのに…」
こんなことを思わずにはいられないくらい、CMやパッケージの印象だけで薬を選ばれている方がほとんどでした。
市販薬を買いに来られる方のなかには「病院に行くのが気まずいから市販薬で済ませたい」と思われている方もいるでしょう。かつての私もそうでした。親にも誰にも知られたくないから市販薬に頼る。でもどれを買ったらいいかわからない。
そんな方たちの助けになりたいと思い、WEBで情報を発信するようになりました。この症状にはどの市販薬がいいのか、どんな症状があったら病院に行くべきなのか、記事を通して少しでも参考にしていただけたら幸いです。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2023/08/23
2023/08/23化膿止めは、怪我したときや火傷したときなどに使われる薬です。市販では数多くの化膿止めが販売されています。
「化膿しているけど化膿止めを使うべき?」「市販ではどの薬を買えばいいの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、どのようなときに化膿止め...続きを読む
-
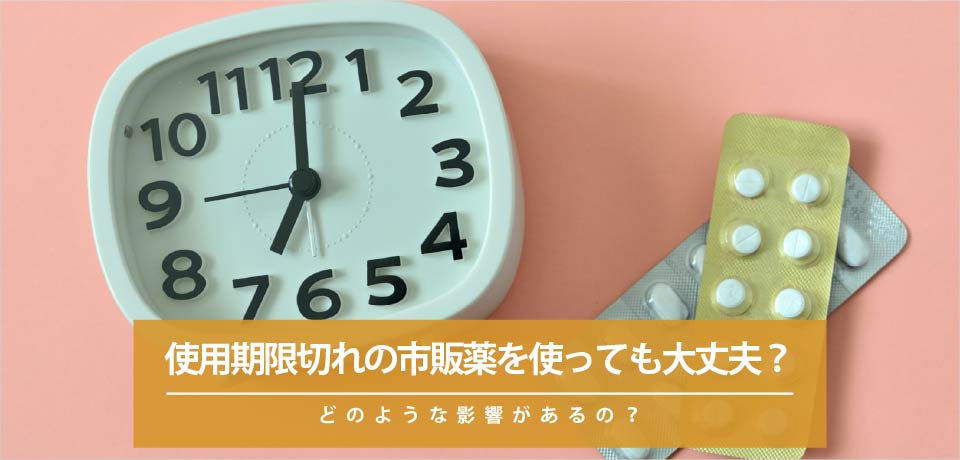 2023/02/06
2023/02/06薬には、必ず使用期限があります。服用しようと思った薬の期限が切れていたり、うっかり期限切れの薬を飲んでしまったりした経験はありませんか?
賞味期限や消費期限とは違い、期限が切れたからといって薬が腐ることはありません。 しかし、「期限切れの市販薬って使っても大丈夫なの?」「使用期限が切れた市販...続きを読む
-
 2024/03/22
2024/03/22「市販薬でも取り扱いはあるの?」と気になっている方が多いのではないでしょうか。下痢や便秘、腹部膨満感などの消化器症状があるとき、ミヤBM錠が手元にあると安心です...続きを読む
-
 2023/03/15
2023/03/15胃酸が上ってきたり、なんとなく胃がムカムカしたりする状態が続いていませんか?逆流性食道炎は、成人の10~20%が罹患しているといわれています。
症状が続くと胃酸で食道やのどがやられて痛みを感じたり、咳が頻繁に出たりするなど、日常生活にも支障をきたす病気です。しかし、忙しくてなかなか医療機関を受診できない...続きを読む




