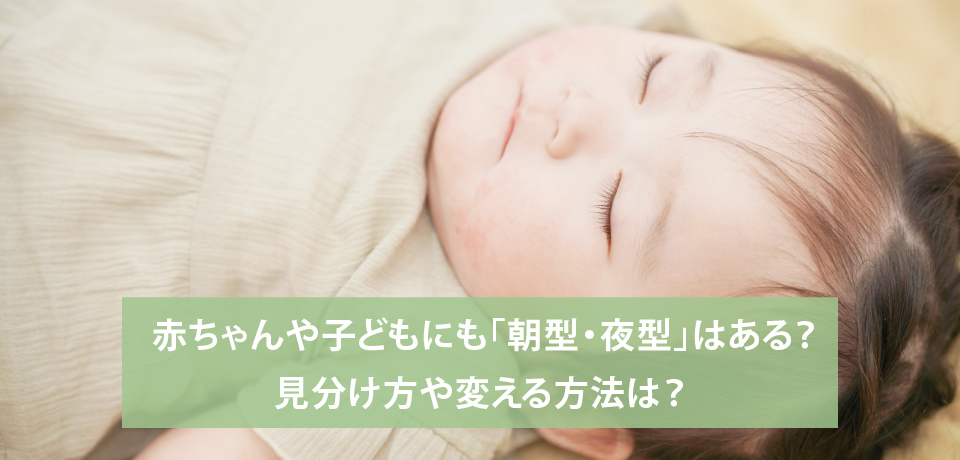
「ママ友の子は毎晩8時には寝るのに、うちの子は11時を回っても目がぱっちりで寝てくれない…夜型だから?」 「子どもが夜なかなか寝ないので家事や仕事が片付かない。朝型に変えられないのかな?」
そんな疑問をお持ちの方はいませんか?
今回は、朝型・夜型は子どもにもあるのか?あるとしたら、夜型から朝型に変えるべきか?などについてを考えていきます。
朝型・夜型とは

皆さんも、なんとなく「自分は朝型かな」「夜型っぽいな」などと考えたことがあるかと思いますが、そもそも「朝型・夜型」の体質というのは本当にあるのでしょうか?
人の睡眠リズムについては近年さかんに研究されており、24時間のあいだにいつ眠くなるのか、いつ目覚めるのか…といったリズムを司る体内時計は、数種の「時計遺伝子」の組み合わせと働きによって決まることが分かっています。
生まれつき、時計遺伝子が朝に活動が活発化する組み合わせの人はいわゆる朝型、夜であれば夜型、昼間の人は中庸型…のように分類され、この分類を「クロノタイプ」と呼びます。
赤ちゃんや子どもの朝型・夜型は決まっている?
1歳頃までの赤ちゃんは、おなかの中にいるときと似た2~3時間ごとに寝たり起きたりする「超日リズム(ウルトラディアンリズム)」という睡眠サイクルをとっていますが、だんだんと昼間起きている時間が長くなり、夜は続けて眠る「概日リズム(サーカディアンリズム)」へ、4歳頃をめどに移行していきます。
子どもはお日様が昇ると同時に元気に起き、日が暮れれば眠くてしょうがないのが健康的…というイメージを持っている方も多いかもしれません。
しかし、生まれつきの遺伝子である程度朝型・夜型が決まっているのであれば、幼児でも遅くまで眠くならないこともあり得ます。
アメリカの研究報告では、2~4歳の幼児約500人を夜型・朝型に分類し、日常生活について調べたところ、朝型の子は寝付きが良く朝も自分で起きてくるのに対し、夜型の子は寝かしつけが難しく、朝もスムーズに起こして出かけるためには何かと工夫が必要で苦労したそうです。
ママ友のお宅では「6時に夕食、7時に入浴、8時に就寝、その後家事や持ち帰った仕事をこなしたり、夫婦でゆっくりドラマを観たりしている」と聞いて、チャレンジするも全くその通りにならずガックリ、あきらめた…というご家庭もあるかもしれません。
しかし、もしかするとやり方が悪いのではなく、単にお子さんが夜型だったのかもしれません。
逆に、家族が遅くまで照明をつけてゆっくり過ごしている家庭では、子どもも夜型の生活を送りがちと言われています。
本来お子さんは朝型なのに家族の影響で夜型になっている可能性ももちろんありますが、なかにはいくら寝かせようとしても寝ないので、結果的にそのリズムになっているケースもあるのではないでしょうか。
夜型の子は朝型に変えるべき?

生まれつき遺伝子タイプは決まっている…と聞くと、いま保育園に通うお子さんのいるご家庭では、
と不安になるかもしれません。
しかしどのタイプでも、ある程度は学校や仕事など外部のスケジュールに合わせて活動できるといわれています。皆さんも、自分自身やお子さんの毎日の生活を振り返り「それはそうだよね、決まった時間に起きるしかないから…」と納得できるのではないでしょうか。
2022年の島根大学の研究でも、大学生が対象ではありますが、どの子も朝型・夜型に関わらず学校の始まる時間までに起き、夜のバイトがあれば遅くまで起きていられる…つまり「社会のリズム」に適応していることが分かっています。
ただし何も予定のない土曜日で比較してみると、夜型の遺伝子を持つ学生は朝昼の活動量が低く、朝型の学生はテキパキと動き回っていて、あきらかに日中の活動量の差があったことが報告されています。
つまり、夜型の子を完全に朝型に変えるのは難しいものの、最低限の社会生活に合わせて寝起きする習慣をつけるのは可能そうですね。
また、朝型夜型にかかわらず就寝時間・起床時間は日々大きく変えない方が睡眠サイクルが乱れにくいとされているため、週末でも適度な時間にはカーテンを開けて起きる習慣を作っておきましょう。
おわりに
今回ご紹介したように、人それぞれ、睡眠リズムや活動するのに向いている時間帯が少しずつ異なることが最近の研究で分かってきています。
まだまだ学校や会社の始業時刻は朝8時や9時と決まっていることがほとんどですが、「各自のベストタイムに勉強したり働いたりできる社会の方が、みんなが生きやすく、生産性も上がるのでは?」という議論も出てきています。
現在の赤ちゃんが大人になる頃には、さらに研究が進み、職場のフレックスタイム制なども普及して、誰もが自分のリズムに合わせてパフォーマンスを発揮できる社会になっていれば良いですね!
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2025/11/11
2025/11/11初めての出産を控えたママ・パパにとって、赤ちゃんのために準備するべきグッズは数多く、いつ何を買い揃えたらいいのか迷ってしまいますよね。
今回は、過去に実施した先輩ママ・パパ50人へのアンケートや体験談も参考にしながら、各種ベビー用品はいつ頃用意するといいのか、またレンタルと購入どちらがいいのかな...続きを読む
-
 2024/04/12
2024/04/12もうすぐ小学校に入学するお子さんのいるご家庭では、初めての子供だけでの通学、ちゃんと通えるかな…と期待と不安を抱いているのではないでしょうか。
また今年ではなく来年・再来年の入学に向けて、公立の小学校に通うのか、私立なのかを検討中のご家庭もあるかと思います。 小学校選びで気になることの1つが「どの...続きを読む
-
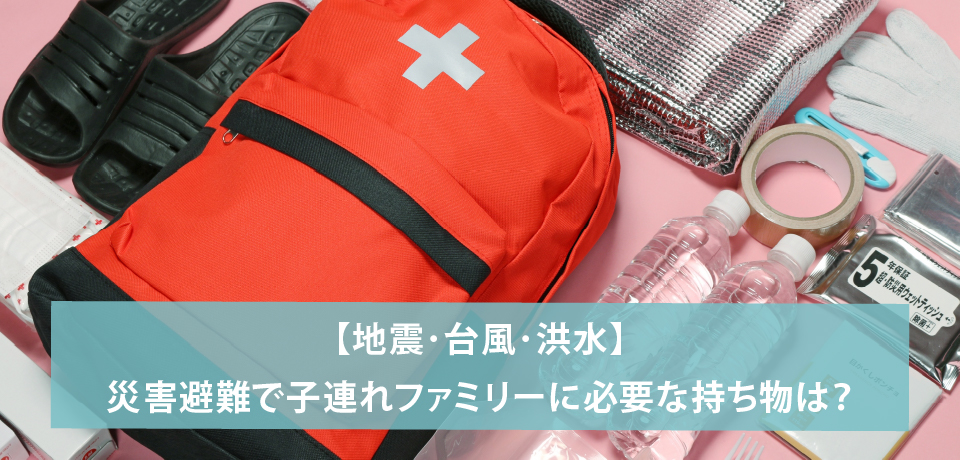 2024/10/09
2024/10/09いざという時のために避難用の持ち出し袋を用意しているご家庭も多いと思いますが、お子さんが小さいと毎日忙しく、なかなか準備できない…という方もいらっしゃるかもしれ...続きを読む
-
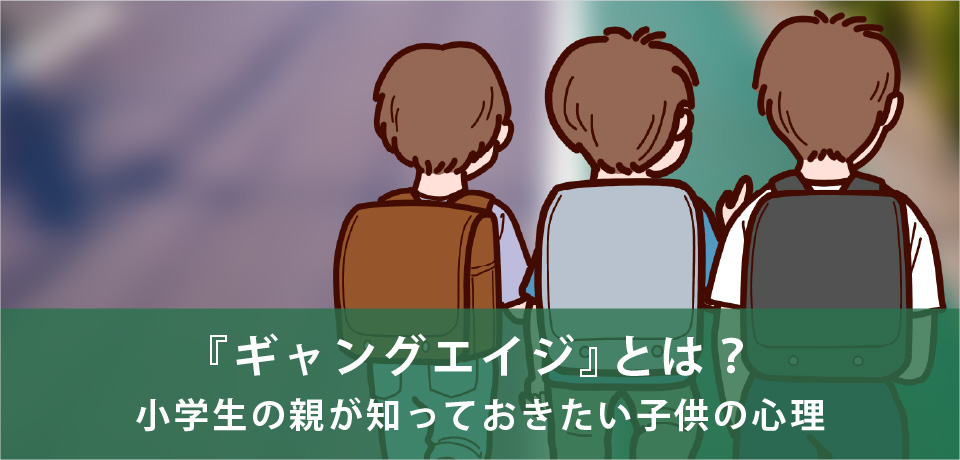 2021/11/10
2021/11/10小学校3年生前後の子供たちは別名「ギャングエイジ」と呼ばれることがあります。なんだかちょっと穏やかでない名称ですが、どんな意味だかご存知でしょうか?
それまではひたすら「ママ、ママ」だったわが子が友達を優先するようになるなど、この時期の子供は急に言動が変化することがあり、戸惑う親御さんもいるかもしれません。 ...続きを読む




