
1歳~2歳にかけてのお子さんの悩みで多いものの1つが「ママや他の子に噛みついてしまう」というもの。
「どうしたらやめさせられる?」
「他の子を噛んでしまったときの対処方法は?」
……など、子どもの年齢と発達から理由を考え、噛むのをやめさせるための言葉がけなどを紹介します。
小さい子が人を噛んでしまう理由や心理

子どもの噛みつきは赤ちゃんから2歳頃までにもっとも多く起こりますが、理由は発達の段階によって様々です。
理由1:歯ぐきの違和感や手の代わり
「噛む」悩みが特に多いのは1歳児・2歳児ですが、0歳児もときどきママの腕などを噛んでくることがあります。
これは、歯が生えてくるときの歯ぐきのムズムズを解消するためと考えられています。歯が生えてきそうなようす(歯ぐきが固くなってくる、よだれが増えるなど)が見られたら、早めに歯固めのおもちゃなどを用意しておくと良いですね。
また五感の1つ「触覚」は、身体の上から下へ順に発達してゆくと言われており、1歳過ぎまでは指先よりも口のまわり(唇・舌・歯ぐき)の方が感覚が鋭い子も多いです。
そのため、この時期の赤ちゃんは何かを手にしたらまずは口に入れて形や固さ・感触などを確かめます。その過程で強く噛むこともあり、それがたまたまママやまわりの子の手や腕だった…というケースです。
理由2:コミュニケーションや愛情表現のつもり
1歳前後の子に多いのが、噛んだ時の相手の反応が楽しいという理由です。
この年代の子はまだ噛まれると痛いという因果関係は分からないため、噛んだら相手が大声を出した・びっくりして飛び上がった、みんなが自分に注目した…などの行動を、赤ちゃんにとっては楽しい遊びのように勘違いしてしまうことがあります。
面白い反応があると、コミュニケーションや愛情表現の一環として繰り返してしまうことも。
理由3:言葉で伝えられないから
0~2歳頃の子どもたちの共通点は、まだ言葉をあまり話せないこと。
「そっちは危ないから行っちゃダメ」と抱きかかえられて怒ったり、おもちゃを取られたくなかったり、楽しい遊びで興奮したり…さまざまな感情を、言葉にして相手に伝えることができず、代わりに噛んでしまうこともあります。
噛むのをやめさせるには?対処方法や言葉がけ

特別な事情がない限り、子どもが人に噛みついてしまう時期はそれほど長くなく、数週間で成長とともに落ち着いてくることがほとんどです。
ただし、他の子やきょうだいなどを噛んで大きな怪我をさせる可能性もありますし、噛まれた子が痛さのあまり思い切り突きとばすなど反撃に出ることもあり、噛んだほうの子も危険です。
まわりの大人は「そのうちおさまるから」と放置するのではなく、その時期は目を離さないで特別注意して見守り、噛みそうになったら止める必要があります。
0歳児への対処方法
前述のとおり、赤ちゃんがママやきょうだいを噛んだ時は、大声を出したりすると楽しい遊びだと勘違いしてしまう可能性があるので、まじめな顔で引き離し「今のはダメだよ」と伝えましょう。
1歳児への対処方法
1歳になると、噛んだ時に叱られれば「自分が悪いことをした」と理解はできます。
とはいえ、噛まれた相手の痛さや嫌な気持ちを想像したり、噛みつきたくなったときに前回叱られたことを思い出して自制したりするのはまだまだ難しい年齢です。
噛む癖があると分かったら、まわりの大人は「特別警戒期間」と考えて、誰かがつねに見守り、噛む前に止めるのがもっとも現実的な対処方法といえます。
保育園に通っているご家庭では、園にも伝えて特別に注意してもらえると良いですね。
2歳児への対処方法
2歳児になると「このおもちゃで遊びたい」「この子が好きだからこっちを向いてほしい」といった欲求や自己主張がはっきりしてきます。
しかしそれを言葉で伝えられるかというとまだまだ難しい子がほとんど。もどかしくて、手っ取り早い方法として噛んでしまうケースがよく見られます。
この場合は、大人が様子を見ておき、噛みそうになったら止めに入って
「〇〇ちゃんが大好きなんだよね。噛んだら痛いから、お手々をつなごう」
など言いたいことを代弁し、噛むのではない方法に誘導してあげましょう。
止めるのが間に合わず噛んでしまった場合、まずは噛まれた子をなぐさめたり必要なら手当をします。
ただし、時間が経つと噛んだ方の子が忘れてしまうので、できるだけ早く「これで遊びたかったんだよね?」と気持ちを代弁し、「でも噛んだら痛いよ」と伝えます。
最後に「噛んでごめんね」「次は貸してほしかったんだって」と意思の疎通をサポートしてあげると良いですね。
おわりに
子どもの噛む癖は、言葉で気持ちを伝えられるようになればほぼ解消します。
しかし小さい子は力加減ができず、噛まれた子はとても痛く怖い思いをするため、その時期だけは最優先で見守ってあげてくださいね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
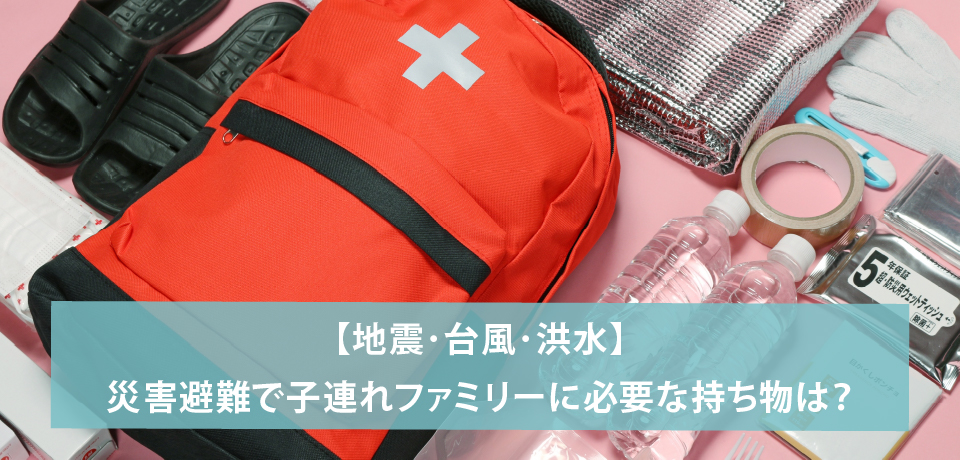 2024/10/09
2024/10/09いざという時のために避難用の持ち出し袋を用意しているご家庭も多いと思いますが、お子さんが小さいと毎日忙しく、なかなか準備できない…という方もいらっしゃるかもしれ...続きを読む
-
 2022/10/05
2022/10/059月は台風シーズンですね。台風の進路に当たってしまい園や学校がお休みになる地域もあるかと思います。
もし子供から「なんで台風が来るの?」「台風はどうやってできるの?」と聞かれたら、どう説明しますか? 今回は、幼児や小学生のママ・パパのため、小さな子にも分...続きを読む
-
 2022/07/20
2022/07/20子供たちの大好きな「おもちゃ」は、ただ遊ぶだけではなく心身の発達にも役立っています。
その中でも「知育玩具」といわれるおもちゃは、年齢に応じて子供のさまざまな能力を伸ばしてくれるのが特徴です。 ただ、お店やインターネットを見るとたくさん種類...続きを読む
-
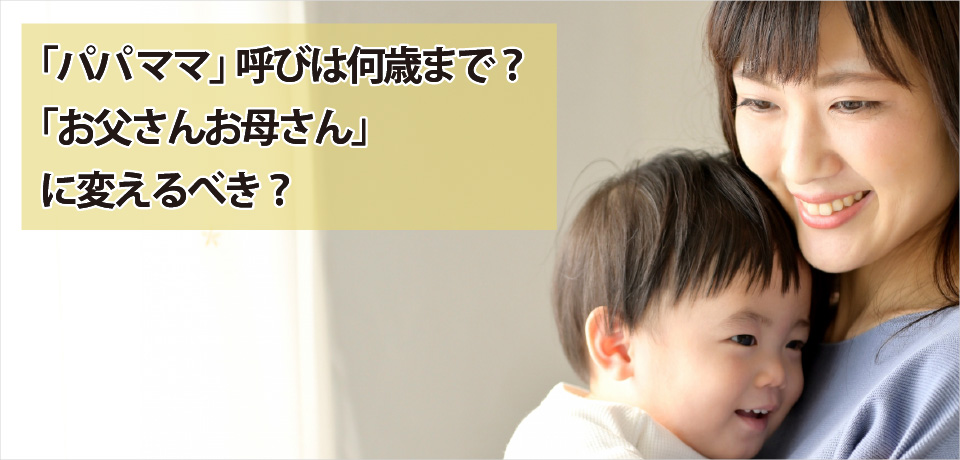 2021/07/02
2021/07/02赤ちゃんが生まれると、毎日のように「ママですよ~」「パパとお風呂に入ろうね」などと呼びかける機会があり、そのうち赤ちゃんも「ママ」「パパ」と呼ぶようになります。
とても幸せな育児の1コマですが、お子さんが成長してくると、ふと「いつまでもパパ・ママと呼ばせていいのかな?」と迷うことがあるかもしれません。 そこで今回は...続きを読む




