
1歳半~2歳頃の離乳食終了から幼児期にかけてのお子さんは、特定の食材を食べたがらないことがよくあります。
「ピーマンなどの野菜を嫌がる」「納豆が苦手で食べない」など、多くの子に好き嫌いはあるものですが、なかでもママやパパが心配なのは、主食であるお米(白米)のごはんを食べないことではないでしょうか?
またこの年代では、逆におかずを残してごはんだけを食べるお子さんも見かけます。
特に小学校入学が近づいてくると、給食で「残さず食べよう」という指導があり困るのでは?と気になる親御さんもいるかもしれません。
そこで今回は、子供が白米を食べたがらない、あるいは白米しか食べようとしないときの理由や対策について紹介します。
1歳・2歳・3歳…子どもが白米を食べない理由は?

子供が白米を食べたがらない理由はいろいろですが、年代によって特有の理由や事情があることも。
離乳食(1~2歳まで)の頃
おかゆや軟版は離乳食に欠かせないメニューですが、最初からべーっと出してしまう子や、最初のうちは食べていたのに、途中から嫌がるようになる子もいます。
しかし、この時期の子供にとって食の嗜好がどんどん変わることは珍しくありません。たいていはしばらくするとまた食べるようになるため、無理強いせず、本当に嫌いになってしまわないよう、うどんやパンなどで代替しつつ様子をみましょう。
幼児食(3歳以上)の頃
3歳を過ぎて大人とほぼ同じ食事を取れるようになってくると、濃い味付けに慣れてきて、味のない(ように感じる)白米を食べなくなる子もいます。
また幼児がなにかに集中できる時間は年齢+1分ともいわれ、興味関心の移りかわりが激しい時期でもあります。あまり食に興味のない子は座って食べること自体に飽きてしまい、白米を食べきるところまで到達しないケースもあります。
なお、赤ちゃんや幼児の米に対する食物アレルギーの割合は卵や牛乳と比べると非常に少ないですが、ゼロではないため、白米を食べると決まって具合が悪くなるような場合は小児科やアレルギー科で相談することをおすすめします。
白米ばかり食べるときはどうしたらいい?

「お米を食べない」という悩みとは逆に「おかずを残してごはんだけ食べる」という子も時々います。
おかずから摂ってほしいタンパク質や鉄分などのミネラル類が不足し、成長に影響するのでは…と、こちらも心配ですよね。
とはいえ、本当に白ご飯だけしか食べていない子は少ないもの。おかずを少しずつでも口にしていれば、まずは心配しすぎず、少しずつ割合を増やしていきましょう。
なお、発達障害の特性の1つに「特定の食材しか食べられない」というものもあり、白い食品(ごはん・うどん・豆腐など)しか口にできない子も存在します。
その場合でも、例えば大根・カブ・ささみ・白身魚など、少しずつ食べられる食材の幅を広げていくことが推奨されますが、けして無理強いはせず、専門家と相談しながら進めていく必要があります。
小学校の給食までに好みは変わるのか

小さいうちは無理に食べさせなくても元気に育っていれば良しとしてきたものの、小学校入学が近付いてくると「給食でごはんを丸々残したら叱られるのでは……」と心配なママ・パパもいるかもしれません。
しかし現在多くの小学校では、食べることが嫌いにならないよう無理に完食させない方針をとっており、昔のように「昼休みになっても食べ終わるまで席を立たせない」といった指導を行うことはほぼないでしょう。
とはいえ、学校給食は望ましい栄養バランスに基づいた献立なので、できるだけ偏らずに食べてくれれば一番ですよね。
幼少期に「白米を食べようとしない」あるいは「白米しか食べようとしない」という状況だった中学生以上のお子さんがいるご家庭を対象に、小学校でのようすをアンケートで聞いてみたところ、以下のような結果となりました。
Q:お子さんは、小学校の給食でごはんとおかずをどちらも食べられるようになりましたか?
- 完全に食べられるようになった…8%
- ほぼ食べられるようになった…22%
- メニューによっては食べられるようになった…41%
- 少しだけ食べられるようになった…25%
- まったく食べられるようにならなかった…4%
Q:食べられるようになった時期はいつ頃ですか?(完全に/ほぼ/メニューによっては/少し)
- 1年生…16%
- 2年生…9%
- 3年生…14%
- 4年生…20%
- 5年生…20%
- 6年生…12%
- その他/食べられるようにならなかった…9%
上記をみると、まったく状況が変わらなかった子はわずかで、約1/3の子はほぼごはんもおかずも食べられるようになり、半分近くの子はメニューによっては食べられるようになったことが分かります。
食べられるようになった時期は1年生から6年生まで色々で、ママやパパからの回答では
「成長とともに食の嗜好が変わってきた」
「スポ少に入り、運動量が増えてお腹がすくようになった」
などが理由として挙げられました。
現在お子さんが小さく、白米を食べたがらない、あるいは白米しか食べないという悩みをお持ちのママ・パパも、成長につれて変化することが分かれば少し安心できるのではないでしょうか。
検診などで発育を指摘された場合は専門家への相談が必要ですが、そうでなければ「食べないと大きくなれないよ!」などと叱らず、気長に見守っていきたいですね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2022/09/14
2022/09/14歯が生え始めたばかりの赤ちゃん。ニコッと笑うと小さな白い歯が見えるのは本当にかわいいですよね。
でも「歯が生えたから、きちんと歯磨きしないと!」と思っても、赤ちゃんが歯ブラシを嫌がったり、ミルクを飲みながら眠ってしまってタイミングを失ったりして、なかなか歯...続きを読む
-
 2021/12/13
2021/12/13赤ちゃんが生まれて、今年はじめてのクリスマスを迎えるママ・パパは、家族でクリスマスパーティをしたいけど、
まだおすわりやハイハイの赤ちゃんでも楽しめるかな?と迷っている方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、離乳食でも雰囲気を味わえるクリスマスケーキや、...続きを読む
-
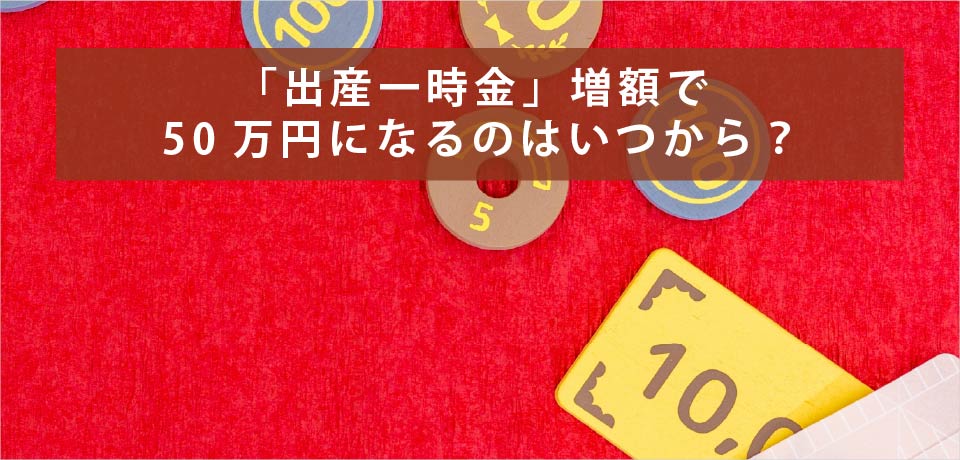 2023/03/10
2023/03/102023年4月には現在の42万円から50万円に金額が引き上げられることになり、注目を集めています。 今回は、これから出産を迎える予定の皆さんのため、制度の...続きを読む
-
 2024/10/23
2024/10/23赤ちゃんの手足の指に、長い髪の毛や靴下の糸くずなどが巻き付いて血流を妨げる「ヘアーターニケット症候群」は、気付くのが遅れると指を失ってしまうおそれもある怖い事故です。
今回は、ヘアーターニケットに1秒でも早く気付く方法や、未然に防ぐ方法を紹介します。 ヘアーターニケットはどんな事故?なぜ起きる? ヘアーターニケットは英...続きを読む




