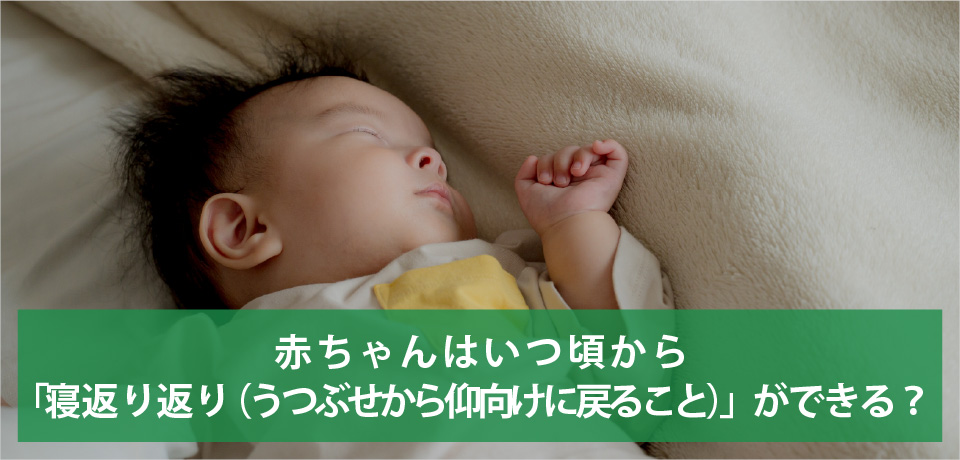
生後すぐは仰向けに寝ているだけの赤ちゃんが、ある時コロンとうつぶせになる「寝返り」。ママやパパも初めて見たときは驚きと喜びを感じることでしょう。
でも、いつまでもうつぶせのままだと赤ちゃんも疲れてしまいますよね。再びコロンと回転して仰向けに戻る動作、つまり「寝返り返り」ができるようになる必要があります。
今回は、寝返り返りは生後何ヶ月頃からできるようになるのか、なかなか寝返り返りができない場合は練習させてあげた方がいいのか……などの疑問にお答えします。
赤ちゃんが寝返りできるまで

赤ちゃんの身体の発達は、基本的に首→腕→背中→腰→足のように、上から下へ順に進んでいくといわれます。
寝返りはまず生後3~4ヶ月頃から首がすわってきて、腕を自分の意志で動かすことができ、背骨と腰骨そして股関節がしっかりしてくることで実現します。
母子手帳の「保護者の記録」欄を見ると、生後6~7ヶ月頃のページではじめて「寝返りをしますか。」という質問項目が登場します。
ということは、平均的には生後半年過ぎには寝返りができている子が多いということになりますが、赤ちゃんの発達には個人差がありますので、その時期の検診で身体機能について指摘されていなければ焦らなくても大丈夫です。
参考
「寝返り返り」は生後何ヶ月頃にできるようになる?
では、寝返りから再び元の仰向けの姿勢に戻る「寝返り返り」は、いつ頃できるのでしょうか。
こちらも個人差はありますが、一般的には寝返りができるようになってから1~1.5ヶ月ほど経ったころが多いようです。
「ちょっと待って!そんなにかかるの?」
と思ったママやパパもいるのではないでしょうか。
寝返りしたあと腹ばいで過ごすには、上半身を支えるための腕や肩・背筋の力がかなり必要。これは赤ちゃんにとっては、最初はなかなかハードルが高いことなんです。そのため、体を支えきれずに布団に突っ伏して泣いてしまう赤ちゃんも。
その都度ママやパパが助けに行き、仰向けに戻してあげないといけませんよね。そして家事に戻ってもまたすぐにコロンと寝返りしては戻れずに泣いてしまう…という体験談もよく聞きます。
「その間は大変そうだ…」と思うかもしれません。
寝返り返りの練習は必要?

ただ、赤ちゃんが1人で元に戻れるようになるまで1ヶ月以上も毎回元に戻してあげないといけないのかというと、意外とそうでもないようです。
何度も寝返りしているうちに、しだいにうつぶせで体を支えていられる時間が増え、片方の腕で体を支えながら反対の手でおもちゃを持つといった動きもできるようになってくる赤ちゃんがほとんど。
片手を持ち上げてバランスが変わった拍子にコロンと元に戻れたのをきっかけに、寝返り返りを覚えていくこともあります。
また中にはうつぶせからそのままずりばい→ハイハイに移行し、ほとんど寝返り返りをしない子もいます。
というわけで、寝返り返りの練習は基本的には必要ありません。あと少しで元に戻れなくてずっと泣いている…という時に、軽く体を揺らして感覚を覚えさせてあげる程度で十分です。
寝返り返りの時期に気をつけたいこと
寝返り返りができるようになると、赤ちゃんの移動範囲は大きく広がります。
回転を繰り返してどこまでも転がっていけるので、柵のないベッドやソファには寝かせないようにしましょう。
2階で過ごす赤ちゃんは階段にもゲートをつけ、リビングでも棚やテーブルにぶつかった拍子にモノが落ちてくると危ないので、ベビーサークルなどを設置すると良いですね。
また誤飲防止のため、床や低い位置に小さなモノを置かないように気をつけましょう。
寝返り返りに限らず他の発達全般にいえることですが、何かが新しくできるようになったばかりの時は思わぬケガや事故の危険性が高まります。特に最初の1週間程度は、赤ちゃんを1人にしておかず、いつも以上に注意して見てあげることが必要です。
おわりに
寝返りができるようになったばかりの赤ちゃんが、うつぶせの姿勢で「いま自分は何をしたんだろう」と言わんばかりに固まってきょとんとしている顔や、寝返り返りしようとしたら片腕が体の下敷きになって戻れずに泣いている姿などは、微笑ましくて思わず笑ってしまいますよね。
成長とともに立ったり歩いたりするようになると、寝返りで部屋の端まで転がっていく姿なども見られなくなります。ぜひ、今のうちにたくさんかわいい様子を見たり動画に撮ったりしておいてくださいね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2024/09/30
2024/09/30小さい子が大好きな「ごっこ遊び」。お家で毎日のようにお店屋さんやお医者さんなど「〇〇ごっこ」をやりたがるお子さんにつきあうのが大変…というママやパパもいるかもしれません。
でも実は、子どもの成長や発達に「ごっこ遊び」は重要な役割を果たしているんです。今回はその理由を解説します。 なぜ小さい子は「ごっこ遊び」をしたがるの? ...続きを読む
-
 2022/05/18
2022/05/183歳を過ぎてくると「自転車に乗ってみたい!」と言う子も出てきて、「どうやって教えたらいいの?」と迷っているママ・パパもいるのではないでしょうか。 今回は、...続きを読む
-
 2022/12/26
2022/12/26出産後、心身ともに不安定な状態の妻に対し、夫が今までと全く変わらず飲み会や自分の趣味を楽しんでいると、妻からの愛情がガクンと下がってしまう……。
当たり前といえば当たり前に思えますが、実はこの時期の愛情低下は「まったくもう!」で済むような一過性のものではなく、その後の夫婦関係に大きく影響し、老後までも左右...続きを読む
-
 2025/12/01
2025/12/014歳頃までの小さい子は、食事や遊びが思い通りにならないと怒って物を投げることがあります。
「人にぶつかると危険」「物が壊れてしまうかも」「食べ物を粗末にする子になってほしくない」…と心配してやめさせようとするものの、なかなか効果がなく悩んでいるママ・...続きを読む




