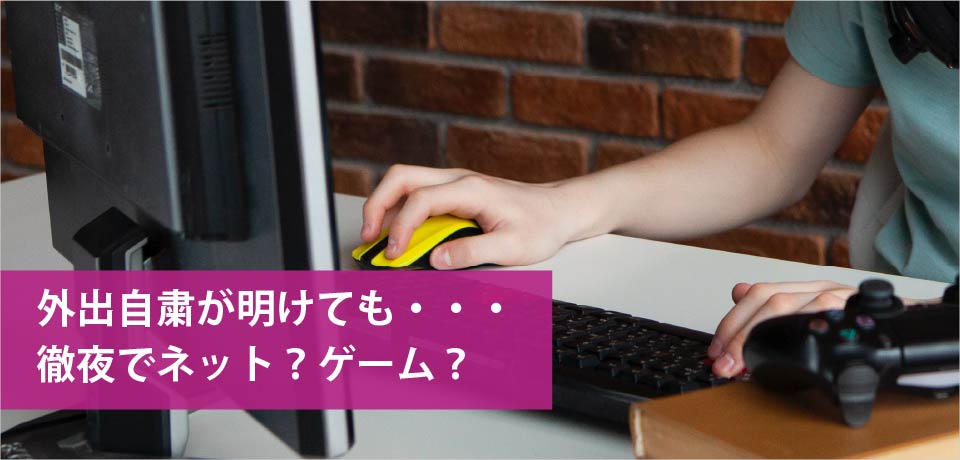
皆さん、こんにちは。加賀谷です。今日は新しい依存症と言われるネット・ゲーム依存に関する話題です。
コロナ禍で外出自粛を要請され、学校にも行けず、友達とも会えず、朝から晩まで家でスマホを使い続けた若者が多いのではないでしょうか。自粛期間が明けてもスマホを使うことを止められず、気がつけばネット・ゲーム依存と言われる状態に陥っているかもしれません。
ネット・ゲーム依存の特徴としては、
出典:久里浜医療センターHP
- インターネットに過度にのめり込み、コンピューターやスマホが使用できないと何らかの情緒的苛立ちを感じる。
- 実生活での人間関係を煩わしく感じたり、対人関係や日常生活に弊害が生じているにも関わらず、インターネットに精神的に没頭する。
ということが挙げられます。
ネット・ゲーム依存の種類としては
出典:久里浜医療センターHP
- リアルタイム型チャット依存:チャットやオンラインゲームなど、利用者同士がリアルタイムにコミュニケーションを行うことを前提としたウェブサービスへの依存
- メッセージ型ネット依存:ブログ・BBS・SNSへの書き込みやメール交換など、利用者同士がメッセージを交換しあうウェブサービスへの依存
- コンテンツ型ネット依存:ネット上の記事や動画などのコンテンツなど、受信のみで成立する一方向サービスへの依存
に分類されるそうです。
熱中しやすいネット・ゲームの特徴
では、熱中しやすいネット・ゲームの特徴は何でしょうか。特定非営利活動法人アスクの調査では、
出典:特定非営利活動法人アスク
- 「ゲーム内コミュニティ」がある
- 「コレクション要素」がある
- 「人対人の対戦モード」がある
- 「チームプレイ」ができる
という特徴が挙げられています。
私が若いころにも、テレビっ子とか、深夜ラジオとか、インベーダーゲームとか、親から見たら問題視されることは多かったと思います。かつてはテレビも深夜ラジオも、送り手の都合で強制終了の時刻が来ていました。でも、今のネット・ゲームはエンドレスに続けることが出来ます。ネット・ゲームを休みの日には1日10時間以上やるという若者も居るようで、『親の立場』としては、「10時間のうち少しでも勉強しろ」と言いたくなるのも無理はないかもしれません。
現実社会で生き辛さを感じたときに、バーチャルな世界に居場所を求めるとも言われています。すなわち、「学校で嫌なことがあった」「友達とうまくいかない」「家族とうまくいかない」「先生に信じてもらえない」など現実社会で多くの困難に直面した時に、ネット・ゲームの世界に楽しい事を見つけてそこが若者の居場所になることがあります。「止めたらゲーム仲間に迷惑をかける」「ゲームの中ではちょっとは有名です」と彼らは言います。ネット・ゲームの世界での責任を果たしたり自尊心が満たされる経験をすると、バーチャルな世界が彼らの居場所として心地よい空間になるのでしょう。

ネット・ゲーム依存の治療はまだまだ手探り状態ですが、それでも一部の医療機関ではテキストを使ったカウンセリングや、リアルな世界での軽作業や、家族支援などを行っています。最近はネット・ゲームに関する相談を受けることもありますが、ほとんどが親からの相談です。しかし、不満ながらも親と一緒に来てくれる若者もきっと「このままではマズい」と考えているに違いありません。思春期や青春期は心理的に疾風怒濤の時代とも言われるくらい感情の荒波に振り回されやすい時期です。自分が思春期・青春期だったころのことを思い出しつつ、ネット・ゲームにのめり込む若者たちの心の奥にある苦悩を理解しようとする姿勢が肝心なのかもしれません。
星の王子さま サンテグジュペリ(作) 内藤濯(訳)岩波少年文庫kindle版
いつかのどこかの17歳 家族のかたちcase01(松尾修)SIGNATURE No.633, 7月号, 22-23, 2020.
コラムニスト|医療法人せのがわよこがわ駅前クリニック 医院長:加賀谷 有行
所在地・アクセス
〒733-0011 広島市西区横川町2丁目7−19 横川メディカルプラザ6F Tel:082-294-8811- JR・広電「横川駅」より徒歩約2分 広島バス「横川駅」または広電バス・広交バス「横川駅前」バス停より徒歩2分
- 横川駅より中広通り経由で約1分 無料駐車場:50台(横川メディカルプラザ内)
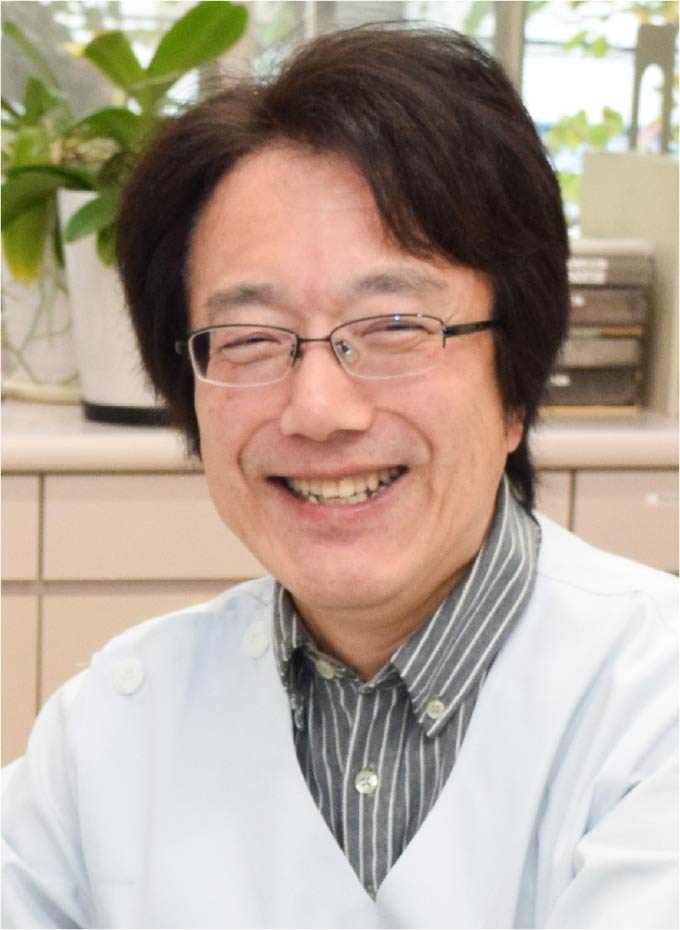
医院長 加賀谷 有行
よこがわ駅前クリニックは2003年7月7日に開業して以来、地域の皆さまの安心、安全を目標にして、真心を持って地域の医療・保健・福祉サービスのお手伝いができるように、こころと身体の両方の相談や治療を実践して参りました。
2024年4月1日より下原篤司先生の跡を継いで加賀谷有行がクリニック院長に就任しました。世の中は先行き不透明な時代になり、児童から高齢者まで各世代で悩みや生きづらさを抱える人が多くなっています。
今後は心療内科・精神科を中心として内科的にも地域の皆さまの早期治療や健康増進に寄与できるよう尽力する所存ですので、よろしくお願いいたします。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
 2020/07/03
2020/07/03皆さん、こんにちは。加賀谷です。 新型コロナに伴う自粛要請が解除されて、自粛空け飲み会なんて企画している人も居るかもしれませんね。やっぱりオンライン飲み会より...続きを読む
-
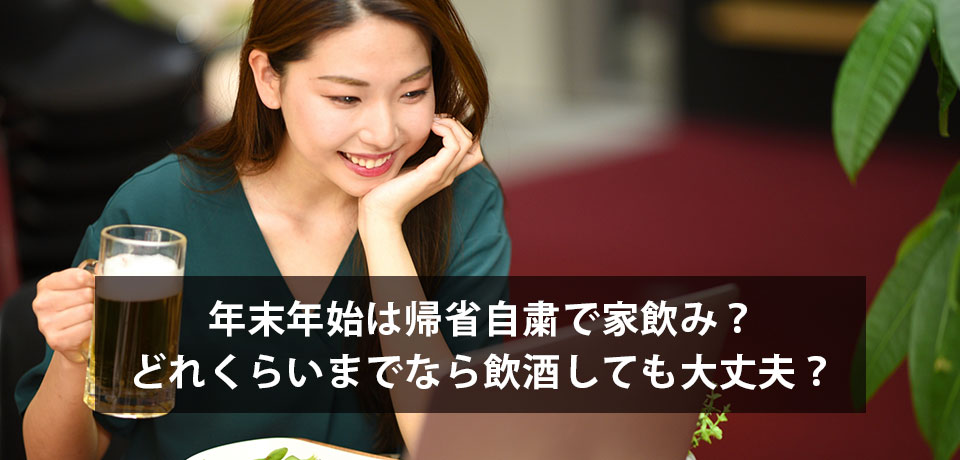 2020/12/15
2020/12/1512月になって広島県内でもコロナ感染者が激増しており心配ですね。
皆さん、こんにちは。加賀谷です。 広島県と広島市では年末年始の帰省の自粛を要請するに至りました。 年末年始の帰省の自粛 今回の集中対策では、感染拡...続きを読む
-
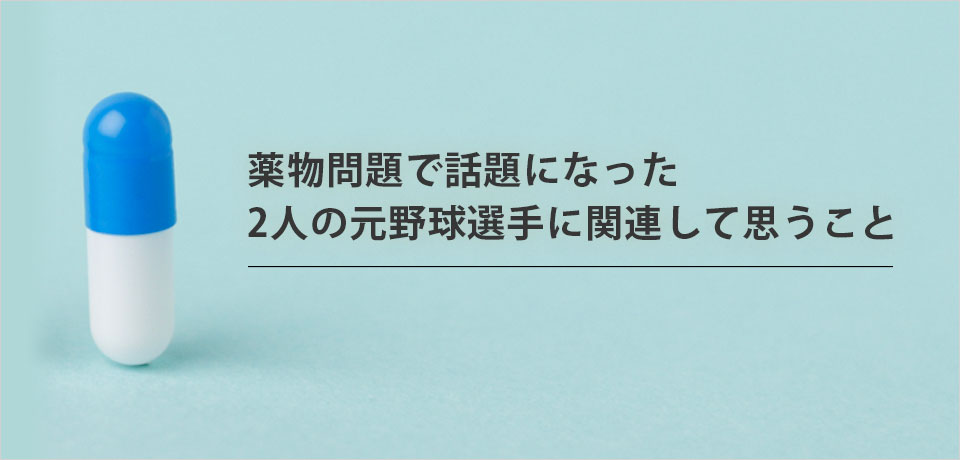 2020/07/14
2020/07/14皆さん、こんにちは。加賀谷です。 広島東洋カープで活躍したジャクソン元選手が大麻所持容疑で逮捕されたそうです。広島時代は笑顔が人気の選手でしたが、あの笑顔...続きを読む
-
 2024/04/05
2024/04/05こんにちは、加賀谷です。3月末にギャンブル依存症がクローズアップされました。
某有名野球選手の通訳Mさんの件ですので皆さんもご存じでしょう。私が驚いたのはMさんの行動について「依存症」という病気に注目した報道がわりと多くみられたことです。...続きを読む





