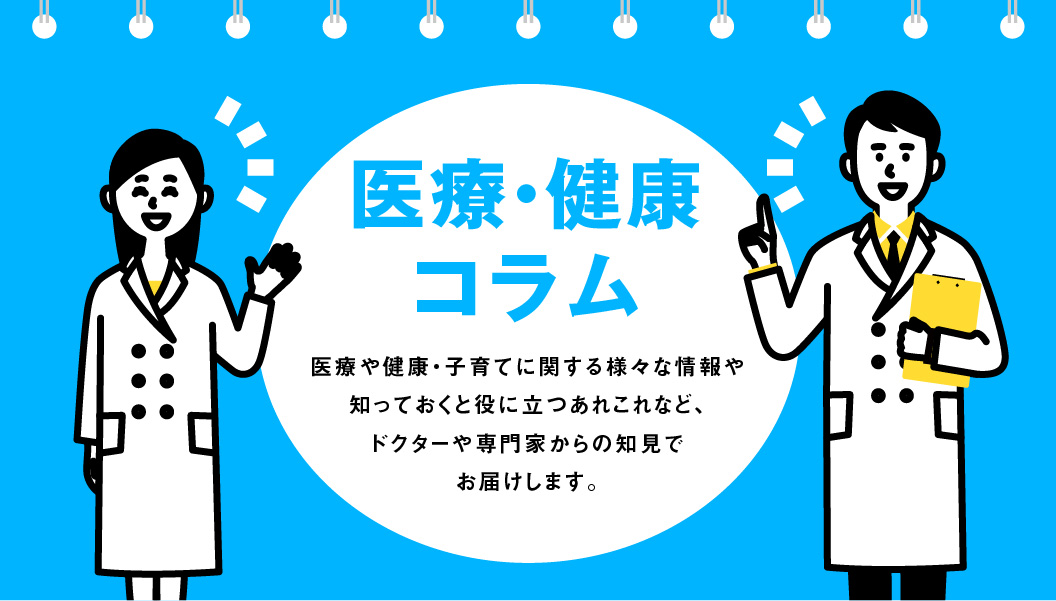- 総合TOP >
- 広島の健康・子育て情報 >
- 作る人も食べる人にもメリハリのある、簡単だけど食欲の湧くレシピです。

作る人も食べる人にもメリハリのある、簡単だけど食欲の湧くレシピです。
天候が不順だと何となくしんどくて、『どうも食欲がなくて』という方もいらっしゃるでしょう。それでも食事を3回規則正しく食べることが、生活のリズムを整えます。老化は20歳代から始まるという説もあります。
最近では20歳代の生活習慣病の方もいらっしゃいます。毎日の、適量でバランスの良い食事と適度な運動が大切です。簡単で良いですから、バランスの良い食事を心がけてください。
(材料は特記がない限り2人分です)
(使用しているめんつゆは2倍濃縮のものです)
前回:あっという間に初夏です。爽やかでバリエーシヨンの豊富な簡単調理を作ってみました。
POINT
- 忙しい日にも、簡単に作れる暑さをしのげるレシピ。
- 調理工程を少なく、できるだけ電子レンジを使うなどして簡単調理。
- 食材は手に入る季節感のあるものを使います。(代用できる食材を明記)
- 調味料も手に入るもので簡単に、また代用できるものを記載しました。
画像をタップするとレシピに移動します。
月曜日の献立

ピーマンの肉詰め
ピーマンは1950年頃から一般に食べられるようになってきた唐辛子の変種です。昔は肉厚でもっと香りのきついものでした。最近では色々改良されて、全く苦みのない子供用の“こどもピーマン”というものもあります。
- ピーマン(大振りで肉厚なもの)2個
- 豚挽き肉 150g
- 玉ねぎ 1/3個
- パン粉 1/3カップ
- 牛乳 大さじ1
- 小麦粉 大さじ3
- 油 大さじ1
- 調味料:白ワイン大さじ2、めんつゆ大さじ1、トマトケチャップ大さじ3、ナツメグ少々、塩・コショウ各少々
- つけ合わせ:キャベツ・舞茸各適量
- ピーマンは縦半分に切って、ヘタと種を取りのぞいておきます。
- 玉ねぎはみじん切りにして、電子レンジで2分位加熱しておきます。
- ボウルに豚ひき肉と玉ねぎ、牛乳でしっとりさせたパン粉、ナツメグ、塩・コショウ各少々を加えて全体がねっとりするまでしっかり練り合わせ、4個の団子状に分けておきます。
- ピーマンは皮の方を下にして並べ、茶こしの中に小麦粉を入れて全体に振りかけておきます。
- ピーマンの中へ、3の挽肉を隅までしっかり詰めて表面に小麦粉をふり掛けておきます。
- フライパンを熱して油を引き、肉を詰めた側から焼きます。
- 表面が焼けたら皮の方を下にして、白ワインを振りかけて蓋をして、弱火で蒸し焼きにします。
- 6~7分して火が通ったら、めんつゆとトマトケチャップを混ぜたものを回しかけて火を止めます。
- キャベツの千切りと焼いた舞茸を添えて盛り付けます。
ピーマンの肉詰めは、本来なら玉ねぎを炒めたり、挽肉の中へつなぎに卵を加えたりしますが、できるだけ簡単に作ってみようと思って省略しました。ピーマンの大きさによって、材料は加減してください。
金平ごぼう(大きいごぼう1本分です)
ごぼうは食用にするのは日本だけのようですが、食物繊維が豊富で水分の吸収率も良いようです。腸内のビフィズス菌も増やします。多めに作れば、副菜に2~3日活躍しそうです。
- ごぼう 200g
- にんじん 1/2本
- 豚肉 60g(適量で)
- ごま油 大さじ1
- 調味料:砂糖大さじ1と1/2、めんつゆ大さじ2と1/2、酒大さじ1
- 七味唐辛子、いりごま(それぞれ好みで)
- ごぼうはよく洗って、皮を包丁の背でこそげて4~5㎝長さの千切りにして、水に浸けます。
- にんじんも同じくらいの長さの千切りにし、豚肉は小さく切っておきます。
- 鍋にごま油を熱して、豚肉をほぐしながら炒めて白っぽく色が変わってきたらごぼうとにんじんを加え、油が全体にまわったら、調味料を加えます。
- 弱火で、混ぜながら炒りつけます。
- 汁けがなくなったら、七味唐辛子を振ります。小鉢に盛り付けてからごまをふります。
ごぼうの独特の香りは皮にあるので、できるだけ皮はむかずに使いましょう。アクが強いので水につけますが、あまり長くつけすぎると香りが薄くなってしまうので、10分位にしておきましょう。
とろろ汁
母がとろろ芋が好きだったのか、子供の頃からよく食べていました。食欲がない時も少し酢を加えて、さっぱりとしたとろろ芋はご飯にかけて食べると食が進みます。
- 長芋 200g
- 酢 大さじ1と1/2
- 調味料:だし汁1カップ、めんつゆ大さじ2、みりん大さじ1
- 焼きのり 少々
- 調味料を火にかけ、ひと煮たちさせて冷ましておきます。
- 長芋は皮をむき、大さじ1と1/2の酢を回しかけておきます。
- あればすり鉢の中へおろしがねをいれて、長芋をすります。(ボウルの中にすりおろして、泡だて器でだし汁と混ぜ合わせても大丈夫です。)
- 1の冷ましただし汁を少しづつ加えながら、すりこぎでよく擦り合わせます。
- 器に盛り付けて、焼きのりを添えます。
山芋はでんぷんを消化するアミラーゼをたっぷりと含んでいます。生で食べた方が効果的です。私はすりおろす際に手が痒くなるのと、山芋のアクが出てくるので酢を使います。少し酸っぱいとろろ汁は食欲がすすみます。
火曜日の献立

鶏のから揚げとフライドポテト
子供たちの大好きなから揚げとフライドポテトです。どうしても高カロリーになりますので、できるだけ衣は振り落として薄くします。
(鶏もも肉1枚分を使います)
- 鶏もも肉 1枚
- 調味料:砂糖大さじ1/2、オイスターソース大さじ1/2、酒大さじ1、ショウガのすりおろし大さじ1、めんつゆ大さじ2、ごま油小さじ1(最後に加える)
- 衣:片栗粉・小麦粉各大さじ3
- じゃが芋(小さいもの)4~5個
- 揚げ油 適量
- もも肉は余分な黄色い脂肪の部分を取り除いて一口大に切ります。
- ビニール袋に調味料を入れて混ぜ合わせ、1のもも肉を加えもみ込んで20分くらい置きます。
- じゃが芋はよく洗って、皮ごと縦に6等分位に切って水に放してからざるに上げて水を切ります。
- 揚げ油を熱して、じゃが芋の水けをふきながら、中温で揚げていきます。
- 次に2のもも肉の中にごま油を加えてもみ込みます。
- ビニール袋に衣用のかたくり粉と小麦粉を入れて振りまぜ、水分を振り落とした5のもも肉を揚げる分づつこの中に入れて衣をつけながら170℃の油で揚げていきます。
- 揚げ油の表面の8割以下くらいの量を、4~5分位かけて順に揚げていきます。
- ペーパータオルに取って、余分な油を切って大皿に盛り付けます。
油は野菜から揚げたほうが傷みが少ないです。また余分な衣が付いていると油を吸って高カロリーになりますし、油自体も汚れます。できるだけビニール袋などで全体に軽くまぶすようにしましょう。粉も無駄になりません。
いんげんと竹輪のさっと煮
さやしんげんは6月~9月が旬です。最近はあまり筋のない品種もあります。カロテンが豊富で分類上は緑黄色野菜の仲間です。冷凍のものも安価でありますので、青みだけでなく煮物などにも使ってみましょう。
- さやいんげん 100g
- 竹輪 1本
- 調味料:めんつゆ大さじ1、砂糖小さじ1/2
- さやいんげんは端を少し折って筋を取り、斜め切りで2~3等分に切ります。
- ちくわは斜めに切っておきます。
- 耐熱皿に入れてラップをし、電子レンジで2分加熱します。
- 小鍋に水をカップ1/4と調味料を加えて煮立て、さやいんげんと竹輪を入れて煮含めます。
- さやいんげんが軟らかくなったら、火を止め、冷めるまでそのままにして盛り付けます。
油揚げなどとしっかり煮つけたい時は、緑の色みが変わっても最初から煮て味を含ませた方が良いです。さやいんげんをごま和えなどにしたい時は、熱湯で色よく茹でたら水に取らないで、ざるに広げるなどして冷ました方が水っぽくならず、美味しく食べられます。
にんじんサラダ
昔はくせの強い野菜で、嫌いな人も多かったと思います。最近は甘くてくせがないように思います。油と一緒に調理するとカロテンの吸収力が高まります。
- にんじん 1本
- 調味料:酢大さじ1、砂糖ひとつまみ、コショウ少々、オリーブ油大さじ2、クミンシード少々(なくても良い)
- にんじんは皮をむいて、千切りのおろし器で細い千切りにしてサッと水に放し、ざるに上げておきます。
- ボウルにオリーブ油以外の調味料を入れて、泡立て器でかき混ぜながらオリーブ油を少しずつ加えます。
- 全体がとろっと混ぜ合わさったら、千切りのにんじんを加えて和えます。
この季節には野菜が傷みやすいので、折角安く購入したにんじんも、うっかりすると表面がぬるっとなることもあります。ラップか新聞紙に包んで、冷蔵庫の野菜室に立てて保存しましょう。
水曜日の献立

レタスと牛肉の炒め物
『レタスが安い!』と喜んで買ってきてもしなっとなってしまうことはありませんか? サラダで食べた後は、炒め物で食べきってしまいましょう。
- レタス 150g(1/2個)
- 牛細切れ肉 200g
- 調味料:めんつゆ大さじ2、コショウ少々
- 油 大さじ1
- レタスは一口大にちぎっておきます。
- フライパンに油を熱して、牛肉をほぐしながら炒めます。
- 牛肉の色が変わってきたら、レタスを加えて、すぐに調味料も加えてひと混ぜします。
- レタスに火が通りすぎないようにひと混ぜしたら火を切ります。
火曜日にオイスターソースを使ったのでめんつゆを使いましたが、オイスターソースだと、又おいしく食べられます。レタスを購入する際は、つい重いものが実が詰まっているように思いますが、あまり硬くて重いものは老化しています。切り口が白くてみずみずしいものを選びましょう。
冷や奴
食欲がない時でもつるっとした絹ごし豆腐ならのどを通りそうですね。食欲がないという高齢者によく勧めます。かつお節やネギだけでなく、色々のせてみませんか?
- 絹ごし豆腐 100gを2個
- 辛子明太子 適量
- みょうが 適量
- ミニトマト 2個
- (その他おろしショウガや千切りの青じそ、小口切りのネギ、塩辛、練ウニ、もろみ味噌等々好みのもので)
- 調味料:めんつゆやしょう油、ポン酢しょう油など
- 辛子明太子は、半分に切ってスプーンを使って皮からしごき出しておきます。
- みょうがは食べやすいように、横にして小口切りにします。ミニトマトは半分に切っておきます。
- 100g程度の大きさに切った豆腐の上に辛子明太子と、みょうが、トマトをのせてよく冷やしておきます。
- めんつゆやしょう油、ポン酢しょう油など好みの調味料をかけていただきます。
冷ややっこで食べる時はできるだけ、新しいものを使いましょう。木綿豆腐は豆乳を固めて水けを切ったものですが、絹ごし豆腐は、濃いめの豆乳を使い水けを切らないで作ったものです。成分的には100g当たり、木綿豆腐が72㌔カロリーでたんぱく質が6.6g、絹ごし豆腐が56㌔カロリー、たんぱく質4.9gと、木綿豆腐の方が栄養価が高いです。
トマトの冷たいスープ
色々な種類のトマトが出回っています。フルーツトマトと呼ばれるものは水や肥料を制限し、糖度を高めたものです。やや小ぶりで甘いトマトを見つけたら丸ごとスープを作ってみてください。
- フルーツトマト 2個
- 調味料:コンソメ顆粒 小さじ1/2
- イタリアンパセリ 2枝
- トマトはヘタの部分をぐるりと包丁の先で切り取っておき、上側の部分に十字に浅く切り込みを入れます。
- 鍋に水1と1/2カップを沸かして、トマトのヘタ側にフォークを刺してこの中へつけて、皮をむきます。
- 2の鍋にコンソメ顆粒を入れて、皮をむいたトマトを加えて湧き上がったら火を止めます。
- トマトとスープをカップに盛り付けます。飾りにパセリを添えます。
子供の頃には、まだトマトは今のように誰もが食べるものではなかったように思います。もちろんミニトマトなどもありませんでしたし、夏だけのもので今のように通年食べられるものでもありませんでした。カロテン、ビタミンⅭが豊富です。
木曜日の献立

竜田揚げ
竜田揚げはしょう油などにつけて、赤っぽく仕上げた肉や魚の揚げ物に使う言葉で、奈良の紅葉で有名な竜田川に由来するとか。
- 鯖(小さめなもの)1尾
- 調味料:めんつゆ大さじ2、ショウガ汁大さじ1、酒大さじ1
- 片栗粉 適量
- 揚げ油 適量
- ピーマン大 1個
- 大根おろし 1/2カップ
- さばは3枚におろして、大きなものなら1枚を3切れに、小さめなら2枚に切ります。
- ピーマンは縦に4~6等分に切っておきます。
- 調味料をビニール袋の中へ入れて、1のさばをつけて、20~30分置きます。
- 先にピーマンは水けを拭いて、高温の油でサッと揚げて得おきます。
- さばの水けをふいて、片栗粉をまぶして170℃位の油で揚げます。
- あまり温度が高くならないようにして、裏返しながら揚げます。
- さばとピーマンを盛り付け、大根おろしを添えます。
味がしっかりついていて、生臭くないので多めに作ってお弁当のおかずにもできます。青魚も高くなりましたが、少し小ぶりなさばは意外に安価です。塩焼きや煮魚より揚げ物にしたほうが、美味しく食べられます。
かぼちゃのいとこ煮
病院の栄養士をしていた頃、『なぜいとこ煮なの?』と聞かれることがありました。調べても分からなかったので『兄弟ではないから、いとこかしら?』と答えることにしていました。
- かぼちゃ 1/4個
- ゆであずき 1パック(100g程度)
- 調味料:砂糖大さじ1、めんつゆ大さじ3
- かぼちゃはワタを除き、食べやすい大きさに切ってから、ところどころ皮をむきます。
- 鍋にかぼちゃと水1カップ、砂糖を入れて落し蓋をして中火で煮ます。
- かぼちゃが軟らかくなってきたら、めんつゆを加えて2分ほど煮てゆであずきを加えて火を止めます。
- 混ぜるとかぼちゃが崩れるので、そのまま冷まし、小豆と共に盛り付けます。
かぼちゃは薄切りで使用する際は、電子レンジで加熱しても時間の節約になりますが、大きなものだと7~8分かかるので鍋で煮たほうがおいしくできます。かぼちゃは硬いので、切り分けるのが大変な時は少し電子レンジで加熱してから切ると楽です。甘く煮た茹で小豆を使う場合は、調味料の砂糖は控えましょう。
きゅうりとみょうがの酢の物
やはり、夏に収穫される夏きゅうりの方が酢の物にしても断然おいしい気がします。ほとんど水分で、特段の栄養はありませんが、爽やかですっきりします。
- きゅうり 1本
- みょうが 1個
- 調味料:酢大さじ2、砂糖小さじ2、塩少々
- きゅうりは板ずり(塩をまぶしたきゅうりをまな板の上で、コロコロ転がします)をして、水洗いをしたら薄い小口切りにして、少し手でもんだら絞っておきます。
- みょうがも薄い小口切りにしておきます。
- ボウルにきゅうりとみょうがを入れて、調味料の甘酢を合わせてかけ、少しおいてなじんだら小鉢に盛り付けます。
忙しい時は、きゅうりは板ずりなしで、小口切りにしたものに塩少々をふり掛けて、しんなりしたらもんで、塩を洗い流し市販の甘酢で和えても良いです。わかめや茹でただけのしらす干しで和えても初夏の一品ができます。
金曜日の献立

豚肉のきのこ巻き
週末が近づくと、そろそろ疲れてがっつり食べたいけど時間かけて作るのしんどいし‥‥。そんな時は冷蔵庫に残っている野菜たちを薄切り肉で巻いて、ご馳走にランクアップしましょう。
- 豚ももの薄切り肉 6枚
- きのこ(エリンギ、舞茸、しめじ、えのきたけ等)適量
- 片栗粉 適量
- ごま油 大さじ1/2
- 調味料:めんつゆ大さじ2、酒・みりん・砂糖各大さじ1/2
- 付け合わせ:トマト2個、玉ねぎ小1/4個、パセリ少々、フレンチドレッシング適量
- きのこは巻きやすいように、小房に分けておきます。
- トマトは1㎝幅に切って、冷蔵庫で冷やしておき、玉ねぎもみじん切りにし、水にさらしてざるに取ります。
- 豚肉をまな板の上に広げてかたくり粉を振り、豚肉の端にきのこをのせて、くるくると巻き、最後にまた片栗粉を振って閉じます。これを6個作ります。
- フライパンにごま油を熱して、豚肉の巻き終わりを下にして中火で焼きます。
- 豚肉を転がしながら焼き付けて、全体に焦げ色が付いたら合わせておいた調味料を流し入れてふたをします。
- 途中で色がついてない所を返しながら、弱火で調味料が無くなるまで炒りつけて火を止めます。
- 皿に盛り付け、付け合わせのトマトはみじん切りの玉ねぎとドレッシングを振りかけてパセリを散らします。
豚肉は下味をつけませんでした。2025年の厚労省の推奨する食塩摂取量は6g/日未満が望ましいとされています。表面に味をつけるだけでも満足感はあると思いますので、できるだけ薄味に慣れてください。
小松菜と油揚げの煮びたし
青菜の中では一番手軽で、安価な野菜だと思います。東京の小松川で作られていたので、この名前が付いているとか。ビタミン類やカルシウムも豊富で、アクが少ないので下茹でしなくて良いので使いやすい野菜です。
- 小松菜 1把
- 油あげ 1枚
- 調味料:めんつゆ大さじ3、砂糖小さじ2
- 小松菜はよく洗い(特に根っこの方)、サッとゆでて3~4㎝に切っておきます。(茹でなくても良い)
- 油あげは熱湯をかけて、軽く絞って油抜きをして、太めの短冊に切っておきます。
- 鍋に水1カップと調味料を煮たてて、油揚げを2~3分煮た後に小松菜を加えます。
- ふたを開けたまま中火で、3~4分煮ます。
- 煮終わったら、余熱で小松菜の色が悪くなるので、濡らした布巾の上に取って鍋底を冷やします。
小松菜は株の張ったものや細いもの、長いものや短いもの等いろんな種類があるようです。和え物、煮物、炒め物、みそ汁の具と何にでも使えますので多めに買ったら。軽く濡らした新聞紙に包んで、ポリ袋に入れて冷蔵庫で保存しましょう。
セロリとあみえびの中華和え
商品名にあみえびと書いてありますが、実はおきあみと呼ばれるもので、エビではなく南極の方で大量に漁獲されるものです。お好み焼きや焼きそばに入れると香ばしくておいしいので、時々買います。安価なものです。
- セロリ 1本(20㎝)
- あみえび 大さじ2
- 調味料:めんつゆ大さじ1、砂糖小さじ1/2、酢大さじ1、ごま油小さじ1、赤唐辛子1本
- セロリは包丁を薄く入れて表面の筋を取って、5~6㎜の斜め切りにしてボウルに入れます。
- あみえびはフライパンで、から煎りをしておきます。
- 赤唐辛子は辛くなるので、種を取って半分にするなど控えめに使ってください。
- 小鍋に調味料を合わせてひと煮立ちさせて、セロリに回しかけておきます。
- あみえびをセロリに混ぜます。
セロリは古代ローマ時代から、整腸、強壮作用のある薬用の植物として重視されていました。現代では肉の臭みを消すスパイスとして重宝されています。ビタミン類やミネラルを含み、特に葉の部分は、栄養的にも優れています。
土曜日の献立

麻婆なす
なすはインドが原産地で、日本には8世紀頃に伝わってきたようです。子供の頃は煮物か、漬物でしか食べたことがなかったような気がします。日本全国で100種類くらいのなすがあるそうです。
- なす 2本
- ピーマン 2個
- 玉ねぎ 1/2個
- 豚挽き肉 150g
- ショウガ 1片
- ニンニク 1片
- ごま油 大さじ1/2
- 調味料:豆板醬大さじ1/2、赤みそ大さじ1、めんつゆ大さじ2、砂糖大さじ1/2、酒大さじ1
- 片栗粉 大さじ1/2
- ショウガ、ニンニクはみじん切り、玉ねぎは1㎝角に切ります。
- なすはヘタを落として、縦半分に切り長めの乱切りにし、水につけてアクを取りざるに上げておきます。ピーマンはヘタと種を取って一口大に切っておきます。
- フライパンにごま油を熱して、ショウガとニンニクを加え香りが立つまで炒めます。
- 3の中へ豚挽肉を加えてよく炒め、玉ねぎ、なすを加えて炒め合わせ、調味料を加えます。
- 3~4分煮て全体がクタっとしてきたら、ピーマンを加えて1分ほど煮て水溶き片栗粉を回しかけ、とろみがついたら火を消します。
長卵なすが一般的で、色々な料理に使えます。長なすは皮も軟らかいですが、実も軟らかいので焼きなすなどにむきます。京都特産の丸なすはきめが細かくて、田楽などにむきます。いつも買うのとは違う野菜を見かけたら、八百屋さんなら使い方を教えてもらえます。
小いわしの刺身
瀬戸内海に面した広島ならではの食べ方だと思います。新鮮な小いわしを見つけたらぜひチャレンジしてください。『七度洗えば鯛の味』と言われています。広島の郷土料理として農林水産省のホームページにも出ています。
- 小いわし 1山(30匹くらい)
- おろしショウガ 1かけ分
- きゅうり 1本
- みょうが 1個
- 調味料:しょう油 適量
- 流水の中で小いわしを、両手でふんわりとこすり洗いをすると、少しついているウロコが剥がれます。
- 手で頭をもって、骨ごと実からはがすようにして引っ張ります。
(荷物を縛る硬いプラスチックのバンドを丸めていわしの肩のあたりからこさげ取ると、身が剥がれます) - 頭と骨を外した小いわしは、氷水の中で何度も洗って残ったウロコや内臓をきれいに洗い流します。
- 再度氷水を用意して、塩を一つまみ加えて3の小いわしを入れて洗います。
- きゅうりの千切りと、みょうがの薄切り、おろしショウガを皿に盛り、ペーパータオルで水けを拭いた小いわしを盛り付けます。
小いわしはプランクトンの多い広島湾で大量に獲れ、6月10日が漁の解禁日だそうです。同じような食べ方をするものに鹿児島のきびなごがあります。これは少し大きくて体長が10㎝近くある美しい銀色の縞模様を持つニシン科の魚です。小いわしはてんぷらにしたり、ショウガで煮たりしても骨ごと食べられて美味しいです。
ゴーヤチャンプル
ゴーヤは別名にがうりと言い独特の苦みがあります。産地は沖縄と宮崎で、この20年位の間に一般的になってきたように思います。6月~8月が旬です。
- ゴーヤ 1/2本
- にんじん 4㎝
- 卵 1個
- 油 小さじ1
- 調味料:めんつゆ大さじ1と1/2、砂糖小さじ1、コショウ少々
- ゴーヤは半分に切ったものを、縦半分に切り大きめのスプーンで種とワタをしっかりかきだします。
- ゴーヤは1㎝弱の厚みの小口切りにします。にんじんはゴーヤより薄い半月に切っておきます。
- フライパンに油を熱して、ゴーヤとにんじんを炒め、火が通ってきたら調味料を加えてかき混ぜた卵を流し入れ、少しおいて卵が固まりかけてきたら全体を混ぜ合わせて火を止めます。
ゴーヤはまだ未熟なものを食用としています。昔ベランダで栽培した時小さなものをそのままにしていたら、赤く熟して、実が割れて中からゼリー状のタネが出てきて甘くなっていました。ワタと種の部分が苦いので、しっかり種と薄皮をこそげ取った方が良いようです。残った半分は薄切りにして甘酢に漬けると常備菜としておいしく食べられます。
豆苗のお浸し
豆苗は中国野菜で、中国では豆苗専用のえんどう豆があるようですが日本ではさやえんどうの種子を使いカイワレ大根のように、大きくなる前のものを水を吸わせたスポンジに生やして売っています。私は2回収穫をします。
- 豆苗 1パック
- 調味料:めんつゆ 大さじ1
- かつお節 適量
- 豆苗は根っこから5㎝位上を切り取って使います。
- 3㎝長さに切って、ボウルに入れて軽くラップをし、電子レンジで1分30秒加熱します。
- めんつゆで和えて、小鉢に盛ったらかつお節をかけます。
本来、オイルやアジアンテイストのものとよく合いますので、ごま油やオイスターソース味にするとおいしく食べられます。生食もできますが、ちょっと青臭い気がします。
何だか天候が安定せず、暑かったり涼しい日があったり、同じ日本列島でも地域によってかなり温度差もあるようです。クリニックで働いていると何の熱かわからないような高熱を出される方も来られます。天候に文句を言っても仕方がないので、上手に自分の生活をコントロールしましょう。3食しっかり食べて、適度な睡眠を取りこの季節を乗り切りましょう!
次回はまだまだ暑い季節が続きますので、なるべくキッチンが暑くならないような簡単なレシピにしたいと考えています。
この記事の監修

管理栄養士 伊藤 教子
ライフワークとして「あなたの体は、あなたの食べたものでできている」ということを意識した「食」の啓発活動を行なっています。
【経歴・資格・所属学会】
※経歴広島大学大学院保健学研究科修士課程修了
介護施設、病院勤務を経て、現在内科糖尿病専門医院にて栄養食事指導に従事。
※資格
管理栄養士 / 日本糖尿病療養指導士
高血圧循環器予防療養指導士 / 栄養相談専門指導士
※所属学会
日本病態栄養学会 / 日本糖尿病学会
日本高血圧学会 / 臨床栄養協会