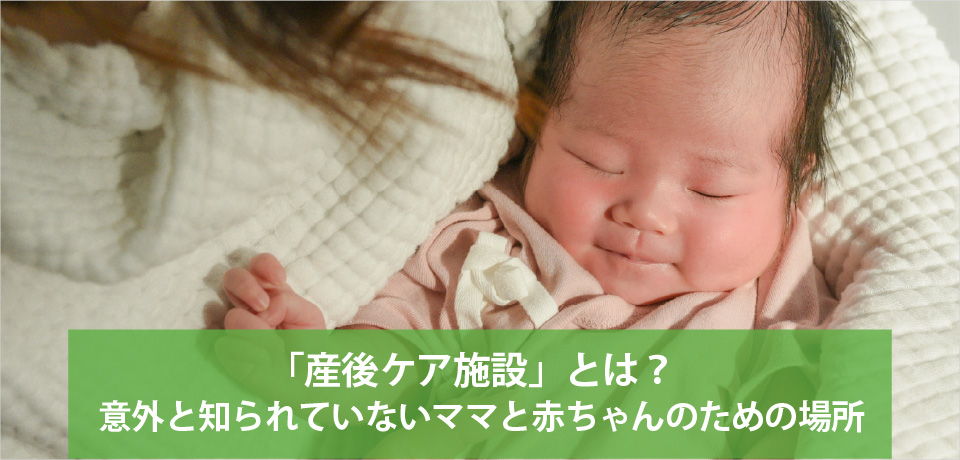
「産後ケア施設」という言葉を聞いたことがありますか?
産院でもなく保育施設でもない、産後のママと赤ちゃんが安全に過ごせる施設を「産後ケア施設」または「産後ケアセンター」といいます。
おもに地域の市区町村が主体となって運営していますが、比較的最近開始された行政サービスであり、自治体によって内容もまちまちなため、知らない方もまだ多いようです。
今回はこの産後ケア施設について、具体的に誰がどんなケアを受けられるのか、利用条件や申請方法などの基礎知識を紹介します。
「産後ケア」とは?

大昔の人類は、集団の中で出産した女性がいれば、産後の身体が回復するまで年上の女性を中心にみんなで身の回りの世話をしたり、上の子の面倒を見たりして生活していました。
しかし、近代の日本では都市部への人口集中や会社員の全国転勤などにより核家族化が進み、家父長制やいわゆる嫁姑問題などで苦しむ人は減りましたが、それと引き替えに、産後のママと赤ちゃんや上の子をサポートしてくれる人がいない家庭も増えました。
もちろん、パパが一番にその役目をしなければいけないのですが、職場で育休を取ろうとすると左遷などをちらつかせて認めてくれない「パタハラ(パタニティ・ハラスメント)」にあってしまったり、パパ本人に親の自覚がなく育児は妻に任せておけばいいと思いこんでいたりで、産後まもないママと子供が孤立してしまうこともあります。
そういった十分なサポートの受けられない家庭のママを支援するため、2019年に母子保健法が一部改正され、産後1年以内の母子に対する「産後ケア事業」が法制化されました。
いろいろな産後ケア施設・産後ケアセンター
産後ケアそのものは幅広い活動が含まれ、例えばほとんどの市町村では、出産後1~3ヶ月頃に保健師が自宅を訪問し、ママの身体や育児で困ったことなどの相談に乗ってくれます。
また地域の子育て支援センターでは「子育てひろば」などが定期的に実施され、赤ちゃんが安全な環境で遊ぶかたわらで保護者も情報交換したり育児の相談ができます。
そして産後ケア施設(センター)では、家族や親族のサポートが受けられないママが赤ちゃんとともに宿泊して心身を休めることができます。
宿泊場所は産婦人科や助産院の空室、ホテルなど自治体によってさまざまです。期間も3~4日から1週間前後と自治体ごとに異なります。
参考
利用には条件も…まずは確認してみよう

出産の肉体的なダメージは交通事故に遭ったのと同程度といわれ、昔から産後3週間ほどの「床上げ」までは赤ちゃんのお世話以外は横になって過ごすのが良いと言われています。
しかし、誰も家のことや上の子のお世話をする人がいなければ、ママは無理して動くほかなく、また夜の頻繁な授乳で睡眠不足も重なった状態では精神的にも辛く、産後うつなどのリスクも高まります。
子供(たち)を安心して誰かに任せて、ゆっくり休めたらどんなにいいだろう…と、多くのママが一度は思ったことがあるのではないでしょうか。
しかし現在のところ、産後ケア施設はいつでも誰でも利用できるわけではなく「家族等から十分な支援が得られない妊産婦」と認められた場合に限られます。
またほとんどの自治体では赤ちゃんの出産後4ヶ月まで(人口や施設の規模により2ヶ月、半年なども)と決められています。
施設や自治体によっては上の子や多胎児(双子、三つ子)を同時に預かれないなど、よりサポートが必要な可能性がある人が利用できないケースも課題となっています。
費用についても、自治体の制度を利用する場合は補助金により比較的安価ですが、回数に限りがあることも多く、民間のホテルの産後ケアサービスは予約さえ取れれば何度でも利用できますが、全額自己負担になることがほとんどです。
申請方法は、コロナ禍を経て、少しずつ自治体のホームページなどから申し込みできるようになってきていますが、当初は市役所の窓口などに出向いて申請する形がほとんどでした。
このような事情から「産後ケア施設へ宿泊してつかの間の休養が取れた」という人はまだまだ少ない状況です。
それでも、国の2020年の調査では産後ケア(日帰り+宿泊)の利用者は出生数に対して約4%だったのに対し、2023年には別の民間の調査で約30%と大幅に増加していることが分かります。
参考
おわりに
「産後ケア施設」の存在は、産院や保健師訪問の際に教えてもらえることもありますが、まだまだ知らない人も多いのが現状です。
数日とはいえ、赤ちゃんを安全に預かってもらいながら休養することは、ママの出産後の心身の回復に大きなメリットがあります。
出産を控えた方や、産後まもない方で「利用したい」と思ったら、まずはお住まいの自治体のホームページなどで、利用条件や申請方法などを確認してみて下さいね。
コラムニスト

認定子育てアドバイザー/育児教育ライター 高谷みえこ
私が結婚・出産を経験したのは今から20年前の2000年。当時は今のようにインターネットやSNSが発達しておらず、育児書以外での情報源は雑誌くらいという限られたものでした。
娘たちが小さい頃はいわゆる「ワンオペ育児(核家族で平日は母親が1人で家事や育児を担うこと)」で、娘たちには喘息やアレルギーなどの持病もあり、当時は本当に毎日大変でした。
親にとって、妊娠~出産から赤ちゃんのお世話や成長発達・幼児の「イヤイヤ期」やトイレトレーニング・園や学校でのトラブル・ママ友付き合いまで、育児の悩みや苦労はその時々で大変大きなものだと思います。
しかし、せっかく工夫してその時期を乗り越えても、子どもの成長ステージにつれ受験や教育費など次々と新しい課題が現れ、過去の悩みは記憶の隅に追いやられがち。次の世代に伝えていく機会はなかなか得られません。
まさに今、かつての自分のように悩んでいるママ・パパがいたなら、自分の経験と知識から少しでも役に立ちたい…という思いから、お役立ち情報や先輩たちの体験談をもとにした解決のヒントなどを、WEBメディアでライターとして発信するようになりました。
より的確で悩みに寄り添ったアドバイスができるよう、NPO法人日本子育てアドバイザー協会の「認定子育てアドバイザー」資格も取得。発達心理学や医学・行政支援などに関する幅広い知識を身につけています。
現在は、育児教育ライターとして子育て情報やコラムを年間100本以上連載中。
かつての自分のように子育てで悩むママやパパへ、正しい知識に基づき心がふわっと軽くなるようなあたたかみのある記事をお届けしていきたいと思います。
 関連記事
関連記事
 関連記事
関連記事-
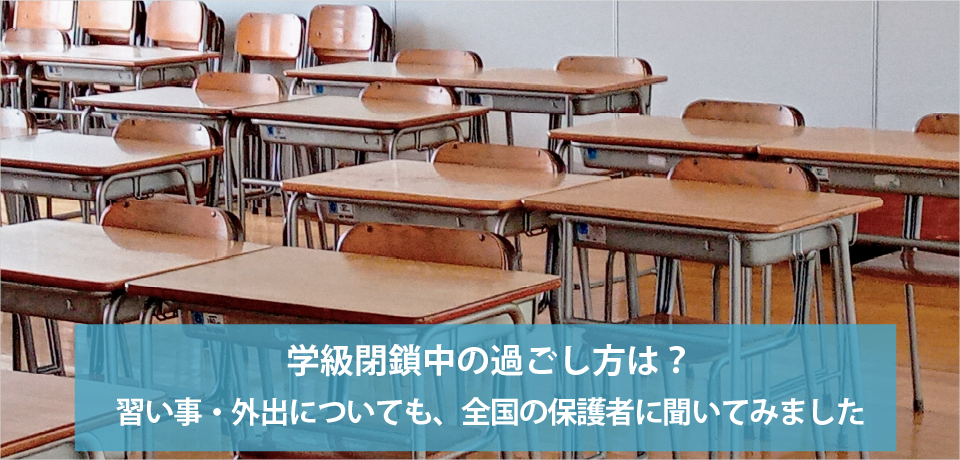 2026/01/06
2026/01/06今年も「インフルエンザ流行中」というニュースが流れる時期になってきました。小学校1年生のお子さんがいるご家庭では、はじめての学級閉鎖を心配している方もいるのではないでしょうか。
また実際に学級閉鎖になった場合、お子さんが元気(症状が出ていない)ときはどうやって過ごすのか、習い事や用事での外出は可能なのか…なども学年を問わず気になるのでは...続きを読む
-
 2024/08/19
2024/08/19赤ちゃんの離乳食や2歳頃までの幼児食には、基本的には唐辛子やワサビなどの辛い調味料は使いませんよね。
その後、3歳・4歳と成長するにつれ、だんだん大人と同じ食事に近付いていきますが、辛い味付けはいつ頃から、どの程度なら食べられるようになるのでしょうか? 実...続きを読む
-
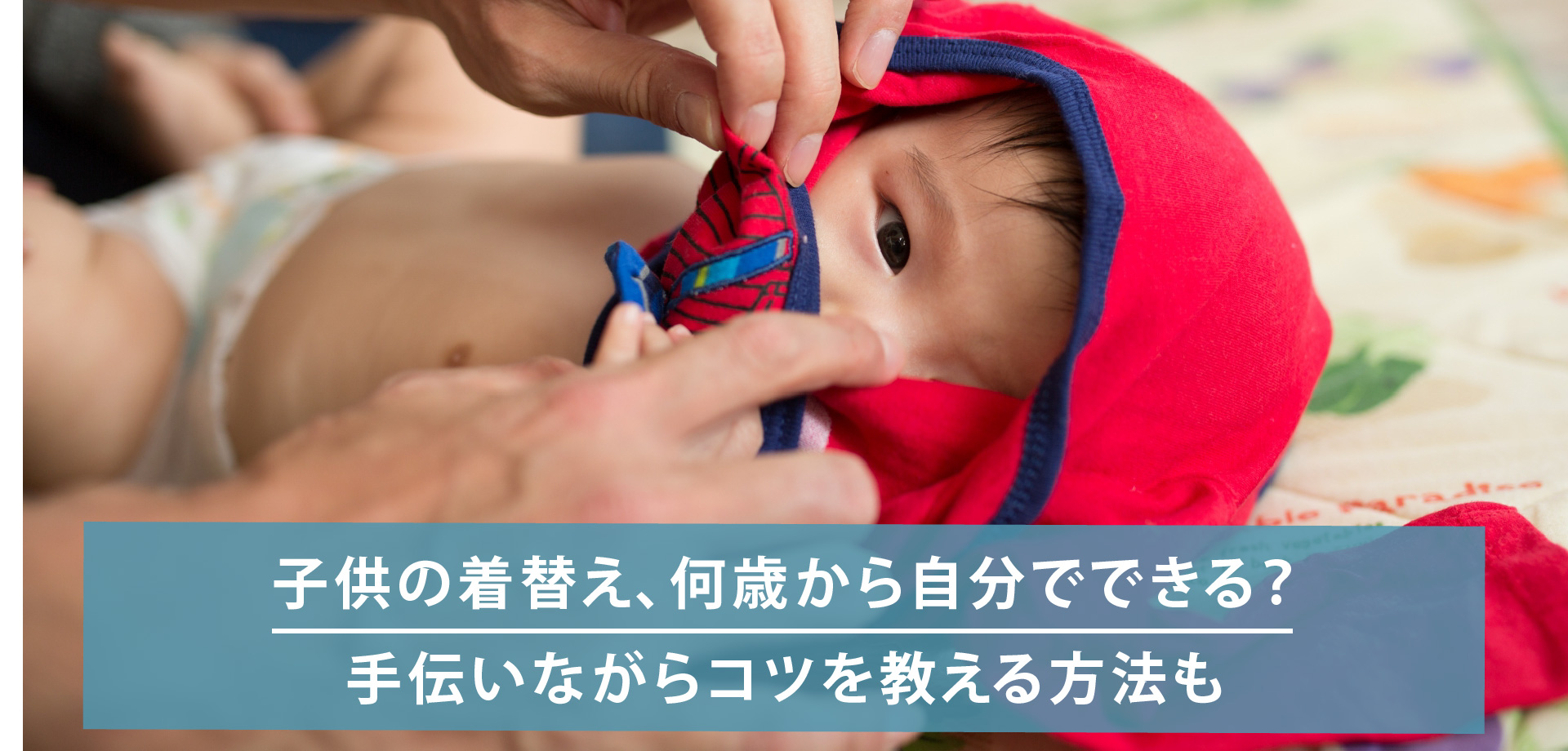 2024/07/03
2024/07/03保育園や幼稚園への朝の登園準備やお風呂上がりなど、子どもの着替えは欠かせないお世話のひとつ。
「時間に追われていつも親が着替えさせているけど、いつごろから1人でできるようになるのかな?」 「最近、自分で着替えたがるけど、なかなかうまくで...続きを読む
-
 2022/10/14
2022/10/14なにもかもお世話してあげないといけない赤ちゃん時代を過ぎ、少しずつ言葉を話したり、身の回りのことが自分でできるようになってくる幼児期。
意志の力も芽生え、あらゆることに対して「イヤ!」と反抗する姿も見られるようになります。 それは順調な成長の証でもあり喜ばしい反面、あまりにも「イヤ!」「イ...続きを読む




